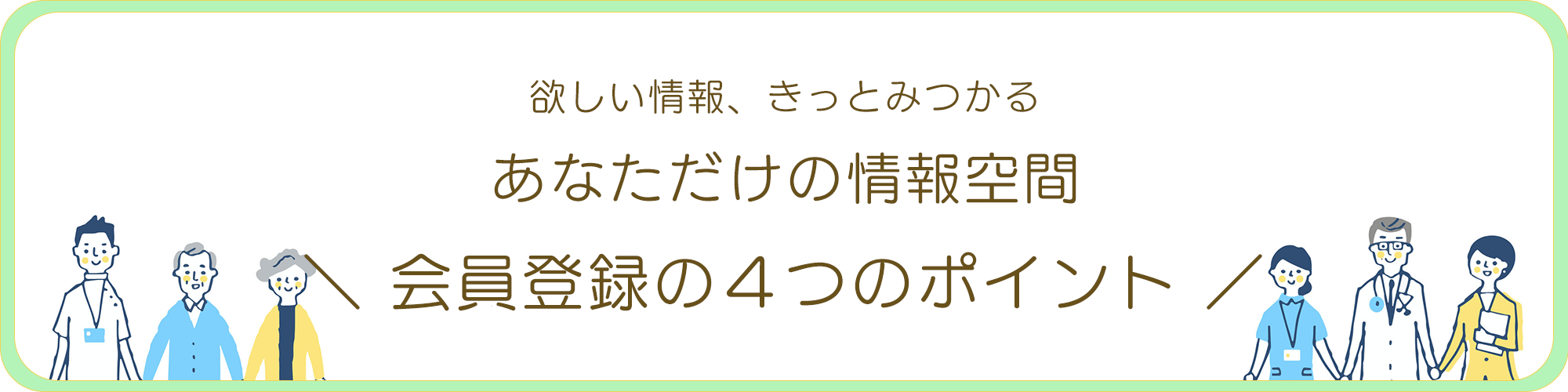居宅訪問型児童発達支援
難病や障害のある0〜5歳児のご家族へ。
「居宅訪問型児童発達支援」は、通所が難しいお子さまのご家庭を訪問して発達支援を行う制度です。制度の概要から申請方法までわかりやすく解説します。
居宅訪問型児童発達支援とは
「居宅訪問型児童発達支援」は、通所施設に行くことが困難な障害や難病を持つ0〜5歳の子どもに対し、専門スタッフが自宅に訪問して発達支援を行う制度です。
たとえば、
- 医療的ケアが必要で外出がむずかしい
- 重度の障害があって移動手段が確保できない
といったケースのご家庭にとって、この制度は大きな支えとなります。
制度の目的
通所が難しい子どもたちにも、発達支援の機会を提供し、早期の成長と家族の負担軽減を目指します。家の中でも、言葉の発達や遊びの支援、食事の練習など、一人ひとりの状態に合ったプログラムが実施されます。
支援内容
0~5歳では、以下のような支援が提供されます。
● 基本的な生活動作の支援:食事、着替え、トイレなどの生活習慣を身につけるためのサポート。
● 感覚・運動の発達支援:リズム遊び、楽器遊び、粘土遊び、水遊びなどを通じて、感覚や運動能力を伸ばす活動。
● コミュニケーション能力の向上:絵本の読み聞かせや簡単な会話の練習を通じて、言語発達を促進。
● 医療的ケアの提供:人工呼吸器の管理や吸引など、医療的ケアが必要な子どもへの支援。
● 家族への支援:保護者への育児相談や、子どもとの関わり方のアドバイスを提供。
居宅訪問型児童発達支援を利用できる人
0歳~5歳未満の児童(乳幼児)で以下のいずれかに当てはまる方
- 重度の障害があるため、通所による発達支援が困難な子ども
- 医師から医療的ケアを継続的に必要とされている子ども
- 難病や希少疾患によって外出が制限されている子ども
たとえば、人工呼吸器を使用している2歳の男の子、てんかんを持つ4歳の女の子など、実際に利用している例もあります。
6歳以上のお子様と異なる支援内容とは?
6歳以上の児童は「放課後等デイサービス」などの支援を受けることが一般的ですが、0〜5歳の子どもは日中の生活支援や基本的な発達支援が中心です。
また、小学校に入る前だからこそ、遊びや親子関係の中で発達を促す働きかけが大切とされています。
居宅訪問型児童発達支援の注意事項
支援制度の利用について、注意しておきたい点を解説します。
- 対象児童の条件:医療的ケアが必要な場合や、外出が困難な障害児が対象となります。自治体によって条件が異なるため、事前に確認が必要です。
- 支援計画の作成:訪問支援を受けるには、相談支援専門員が作成する「障害児支援利用計画案」が必要です。
- 利用手続き:自治体の福祉窓口で申請し、受給者証を取得する必要があります。申請時には診断書や障害者手帳の提出が求められることがあります。
- 訪問支援の頻度:週2回程度の訪問が一般的ですが、児童の状態に応じて調整されます。
- 費用負担:原則として利用料の1割を負担しますが、所得に応じた上限が設定されており、低所得世帯は無料となる場合があります。
- 家族との連携:保護者との面談を定期的に行い、支援の効果を確認しながら計画を調整します。
こんなケースでは対象外になる可能性も
- 一時的に外出が難しい(風邪など)の場合
- 医療機関への通院は可能である程度の移動ができると判断された場合
利用を希望しても、自治体が「居宅訪問型ではなく通所可能」と判断することがあります。
制度利用の問い合わせ先
申請・相談はお住まいの市区町村の障害福祉課または子ども家庭支援課が窓口となります。
どの自治体でも、事前に電話での予約相談を受け付けているケースが多く、親切に対応してくれます。
居宅訪問型児童発達支援の申請方法
- 市区町村に相談(福祉課)
お住まいの自治体の障害福祉課や相談支援事業所に相談し、申請を行います。必要に応じて聞き取り調査が実施されます。 - 害児支援利用計画案の作成
相談支援事業所に依頼して「障害児支援利用計画案」を作成してもらいます。保護者が自分で作成することも可能です(セルフプラン)。 - 支給決定
自治体が申請内容を審査し、サービスの支給量などを決定します。決定後、「福祉サービス受給者証」が交付されます。 - サービス提供事業者を決定
相談支援事業所がサービス提供事業所と連携し、計画を作成します。利用する事業所を選択し、契約を行います。 - 居宅訪問型児童発達支援スタート!
計画に基づき、居宅訪問型児童発達支援のサービスが開始されます。定期的にサービスの見直し(モニタリング)が行われます。
申請時のポイント
- 対象児童の確認:医療的ケアが必要な場合や、外出が困難な障害児が対象となります。自治体によって条件が異なるため、事前に確認しましょう。
- 支援内容の理解:訪問支援員(保育士・看護師・理学療法士など)が提供する支援内容を把握し、子どもの発達に適したサービスを選びます。
- 費用負担の確認:原則として利用料の1割を負担しますが、所得に応じた上限が設定されており、低所得世帯は無料となる場合があります。
まとめ
「居宅訪問型児童発達支援」は、外出が困難な0〜5歳のお子さまとご家族にとって大きな助けとなる制度です。通所できないからといって、発達支援を諦める必要はありません。まずは自治体の窓口に相談し、お子さまの状態に合った支援を受けられるかどうかを確認しましょう。
【参考】