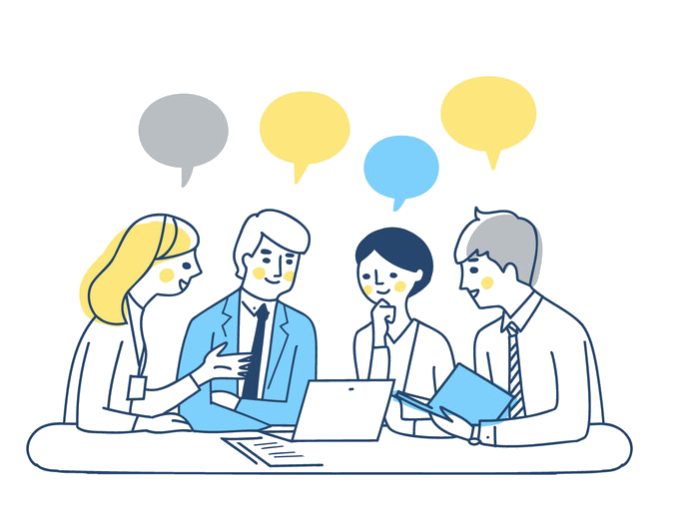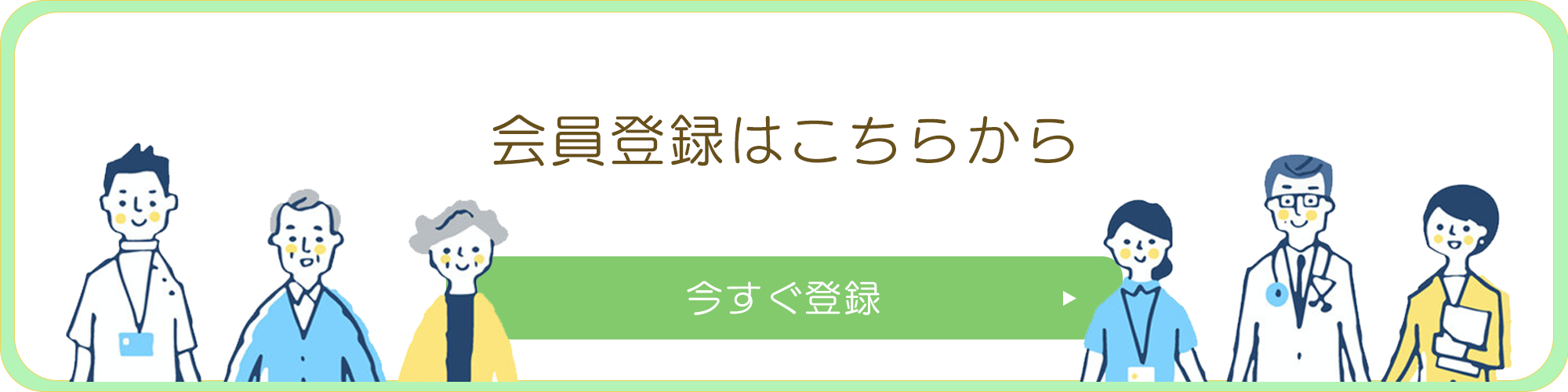難病があっても働ける?|働いている人の割合・職場環境・仕事の見つけ方を解説
2025/4/4 公開
2026/1/5更新
難病があっても働いている人はたくさんいます
「難病があると働くのは難しい」と感じる方も多いですが、実際には多くの人が仕事をしています。
ある大規模な調査では、難病患者の70%前後が治療と両立しながら働いているという結果がありました。これは治療で症状を抑えつつ、就労している方が多いことを示しています。
また、企業で義務づけられている「障害者雇用率制度」は、今後、障害者手帳を持たない難病患者も対象に含める方向で議論されています。これは難病のある人の就労を社会全体で支える動きが進んでいることの表れです。
※ただし、統計データは調査方法や対象によって幅があり、100%の人数を確定するものではありません。
▼参考サイト:
難病でも症状抑えれば働ける 「障害者と健常者のはざま」で悩む人も(2025/5/23)(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/AST5Q1SX6T5QUTFL007M.html
手帳持たない難病患者も障害者雇用率に算定、厚労省が検討 就労継続の難しさは同等(産経新聞)
https://www.sankei.com/article/20251003-JB3BDIL5QBNKPONTXSF4WYXF4U/
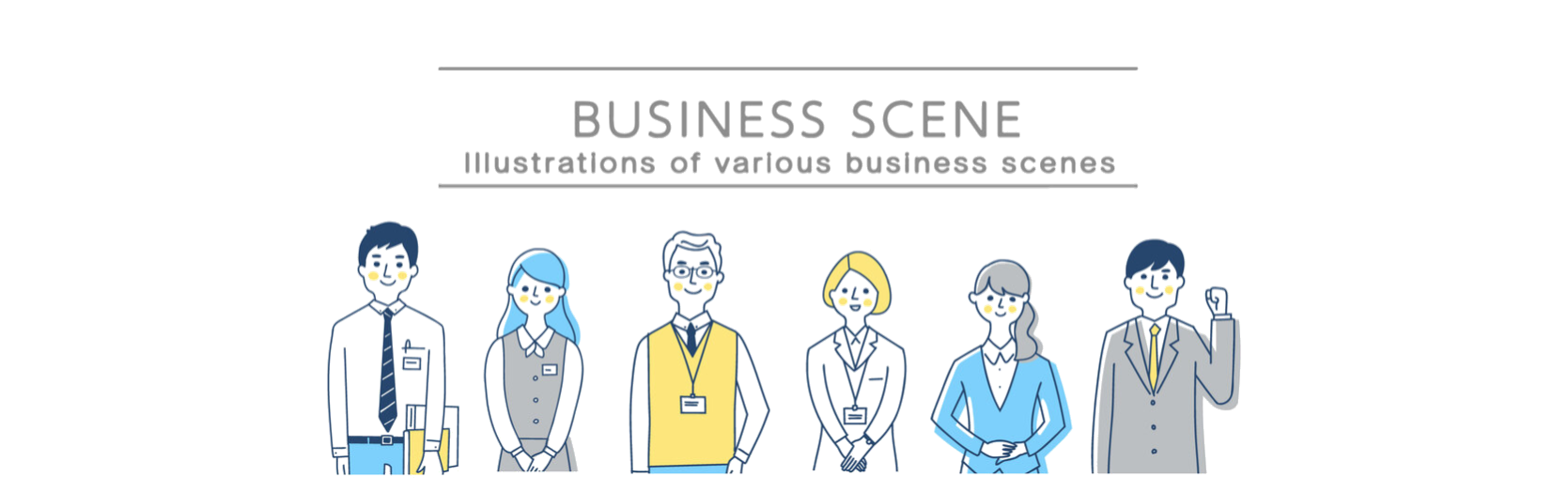
難病患者が働きやすい職場とは?就労支援と環境のポイント
難病のある人が長く働き続けるためには、働きやすい職場環境が欠かせません。ここでは、難病患者の就労支援の視点から、働きやすい職場のポイントを整理します。
1.疾患の影響に配慮した環境
難病は症状や体調が日によって変わることがあります。そのため、通院や体調不良の際に休みが取りやすく、勤務時間や休憩の調整が相談できる職場が望ましいです。
厚生労働省の資料では、ハローワークに配置された「難病患者就職サポーター」などが、症状に応じた就労相談や職場定着支援を行っていると紹介されています。
▼参考リンク:
難病患者の就労支援(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146556.html
2.柔軟な働き方が可能
在宅勤務、時差出勤、短時間勤務など、働き方を柔軟に選べることも重要です。日本財団ジャーナルでは、症状の波や通院に合わせて勤務スタイルを調整できることが、長期就労の継続に役立つと指摘されています。
▼参考リンク:
難病があっても、働きたい。「両育わーるど」が目指す、誰もが働きやすい社会とは?(日本財団ジャーナル)
https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2025/112720/intractable_disease
3.職場全体の理解とサポート
症状や治療ペースの個人差を理解し、安心して相談できる環境も必要です。難病者の社会参加白書では、上司や同僚とコミュニケーションを取りやすい職場環境が、働きやすさにつながると報告されています。
▼参考リンク:
難病者の社会参加白書2025(両育ワールド)
■難病患者の就労を支える制度・支援サービス■
・ハローワークや就労支援機関による個別相談
・難病患者就職サポーターによる職場適応支援
・在宅勤務や時差出勤などの柔軟な勤務制度
これらの支援を活用することで、症状の波や職場理解の不足といった課題を克服し、長く働き続けることが可能になります。
難病がある場合、仕事はどうやって見つける?
一人で進めるより、支援をうまく活用することがポイントです。
① 主治医と相談する
まずは自分の病状や治療計画について主治医と話し、
・どれくらい働けそうか
・通院との両立が可能か
を確認します。これは就職活動でも重要な判断材料になります。
② 就労支援機関に相談する
以下のような専門窓口を利用できます:
・障害者就業・生活支援センター:仕事探しの相談、求人紹介、職場定着支援など
・ハローワークの障害者窓口:難病に理解ある求人の紹介やサポート
・就労移行支援事業所:就職準備や職場実習など支援が受けられる
大阪府など自治体でも、難病のある方の就労支援制度が整っていると案内されています。
これら支援機関は、体調に配慮した働き方や求人を紹介してくれるだけでなく、面接対策や職場との調整サポートなども行ってくれます。
▼参考サイト:
難病患者への就労支援について(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/o100040/chikikansen/nanbyo/nanbyo_shigoto.html
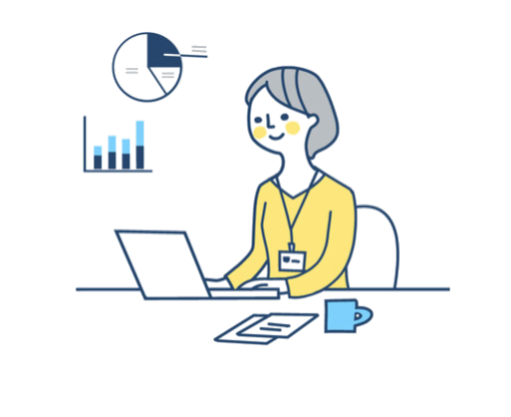
自分の条件を整理する
仕事探しでは、事前に次のような点を整理しておきましょう:
・週に何日・何時間働けるか
・通勤は可能か、在宅勤務が良いか
・体調が悪い日はどう対応したいか
「完璧に働くこと」ではなく、「無理なく続けられる条件」を重視することが、ミスマッチを防ぐコツです。
まとめ|難病があっても働く道はある
難病がある方でも、多くの人が働きながら生活しています(約7割規模の調査あり)。
働きやすい職場は、体調に配慮した環境や柔軟な働き方ができることがポイントです。
また、支援機関に早めに相談することで、求人情報や職場調整、面接対策などが受けられ、就活がスムーズになります。
一人で悩まず、利用できる制度や支援をうまく取り入れることが、無理なく働き続ける鍵です。