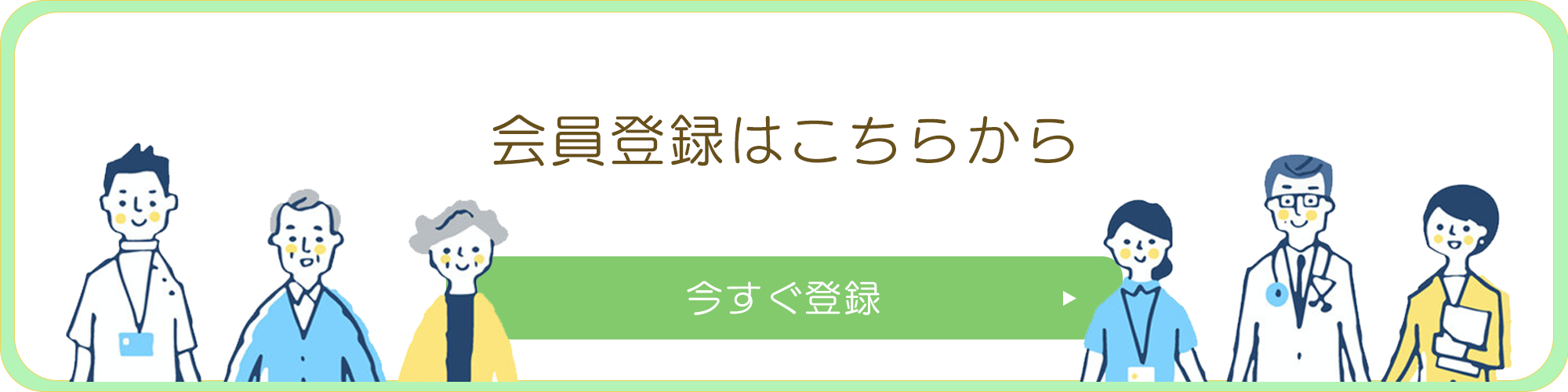障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)

豊島区での制度の概要
豊島区では障害のある子どもの生活に対応するため、児童福祉法に基づいたさまざまな障害児通所支援サービスを提供しています 。これらのサービスは子どもの成長段階や障害の種類、程度に応じて利用することが可能です。
豊島区で提供している各サービスの概要を紹介します。
児童発達支援
日常生活における基本的な動作や知識技能の習得・集団生活への適応のための支援をし、また身体に不自由のある児童についてはこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援
自宅を訪問して、日常生活における基本的な動作や知識技能の習得・生活能力の向上のために必要な支援を行います。
保育所等訪問支援
学校や幼稚園、保育所など子どもが通う施設を訪問し、保育所等における集団生活への適応のための専門的な支援を行います。施設のスタッフに対しても障害のある子どもへの接し方などアドバイスを提供します。
放課後等デイサービス
学校通学中の障害児について、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な支援や社会との交流の促進等を継続的に提供します。これによって学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。
障害児通所支援サービスの利用料は原則としてサービス費用の1割が自己負担となり、世帯の住民税所得割額に応じて月額の上限が定められています(※1)。
ただし未就学児(0歳から小学校入学まで)については以下のとおり豊島区では独自に利用者負担額軽減措置を実施しています。
- 0歳から3歳の子ども:豊島区独自の助成により、3歳の3月31日まで利用者負担額は0円となります。
- 3歳から5歳の子ども:国の無償化制度の対象となるため、3歳の4月1日から小学校入学までの期間は、利用者負担額は0円となります。
そのため豊島区では、未就学の子どもが障害児通所支援サービスを利用する際の自己負担額は原則無料となっています。
ただし、サービス提供時にかかった医療費や教材費、軽食費などは自己負担が発生します。
豊島区で利用できる対象者
制度の対象者はまず豊島区にお住まいであること、そして各サービスごとに条件が定められています。利用したいサービスごとに年齢や状態をご確認ください。
児童発達支援
対象者は、療育の観点から集団療育および個別指導を行う必要があると認められる未就学児です。各種障害者手帳または医師の診断書等により療育の必要性を確認します。
居宅訪問型児童発達支援
対象者は、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定められる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援または放課後デイサービスなどを受けるために外出することが著しく困難であると認められた児童です。未就学児、就学児ともに利用可能です。
保育所等訪問支援
対象者は、保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児であり、かつ当該施設において専門的な支援が必要と認められた児童です。未就学児、就学児ともに利用可能です。
放課後等デイサービス
対象者は小学1年生から高校3年生までの学校に在学している児童です。
各種障害者手帳または、固定級の在籍証明書・支援級の通級証明書、医師の診断書などにより支援の必要性を確認します。
豊島区での制度利用の窓口
障害児通所支援に関する相談もしくは申請を行いたい時は、下記の窓口にお問い合わせください。
●豊島区 障害福祉課 児童・障害児支援グループ
・所在地:豊島区南池袋2-45-1(区役所4階)
・電話番号:03-4566-2451、FAX:03-3981-4303
豊島区での申請方法
豊島区で障害児通所支援サービスを利用するための基本的な流れは以下の通りです。
1. 電話相談
まず豊島区役所障害福祉課児童・障害児支援グループ(03-4566-2451)に電話で相談し、制度概要や申請手続きについて確認します。
2. 事業所の見学と選定
利用を希望する障害児通所支援事業所を見学し、サービス内容や雰囲気、空き状況などを確認します。利用する事業所は、豊島区外でも構いません。
そのうえで利用したい事業所と、利用したい曜日や時間などを決めます。
3. 必要書類の準備・提出
下記の書類を準備し、申請時に提出する必要があります(※2)。
1).障害児通所支援申請書
2).世帯状況申告書
3).決定時調査票
4).現況調査票
5).サポート調査票
6).セルフプラン(※障害児相談支援を利用しない方のみ)
7).障害児計画相談支援申請書、もしくは計画相談支援依頼(変更)届出書(※障害児相談支援を利用する方のみ)
8).資格要件(各種障害者手帳や医師の意見書・診断書、通級証明書等)
4. 受給者証の申請・面談
豊島区へ障害児通所支援の受給者証を申請します。
申請後、豊島区役所の窓口で職員による面談(30分程度)を受けます。そのため申請前に電話で連絡し、日程を調整しておく必要があります。
5. 受給者証の交付
申請内容が審査され、通常2週間程度で受給者証が交付されます。
これをもって申請手続きは終了です。
※1 障害児通所支援の利用者負担について|豊島区
https://www.city.toshima.lg.jp/503/documents/riyousyahutann.pdf
※2 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)申請書ダウンロード|豊島区
https://www.city.toshima.lg.jp/503/2305241542.html