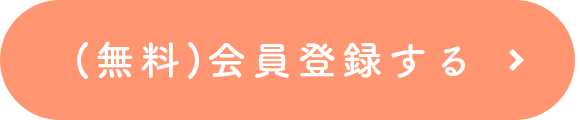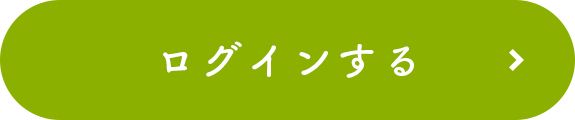在宅難病患者医療機器貸与事業

在宅で療養を受けている難病患者さんは、常に同じ病状ということはなく、時には在宅にはない医療機器が必要になることがあります。
そんな時、医療機器の購入や、通院・入院などにお金や時間をかけず、一定期間貸し出しを受けて自宅で使用することができたら、負担が少なく安心ですよね。
この記事では、豊島区にお住まいの難病患者さんに向けて「在宅難病患者医療機器貸与事業」の仕組みや対象者、注意点などについて分かりやすく解説していきます。
いざという時焦らなくて良いように、相談窓口や申請方法も記載していますので、参考にしてみてください。
豊島区での制度の概要
「在宅難病患者医療機器貸与事業」では、在宅難病患者さんが在宅で必要とする医療機器を貸与し、併せて必要に応じ週1回を限度とした訪問看護を実施します。
これは、患者さんの在宅療養環境の充実と安定した療養生活の確保を図り、患者さんの医療と福祉の向上の助けになることを目的としているものです。
この制度で貸し出し可能な医療機器は、
- 吸入器
- 吸引器(中度・重度・最重度の3機種)
の2つで、無料で貸し出しをしています。
そのおかげで、患者さんとその介護者(ご家族等)の経済的負担が軽減できますね。
貸与期間は、知事が貸与を決定した日の属する年度内において、知事が必要と認めた期間となります。(更新できる場合もあります)
豊島区で利用できる対象者
豊島区での「在宅難病患者医療機器貸与事業」の対象者は、以下の①〜③すべてに当てはまる方です。
①東京都内に住所を有する方
※ただし、豊島区に住所がある方は豊島区に申請します。他の区の窓口では申請できません。
②指定難病、または東京都難病医療費等助成対象疾病にかかっている方で、在宅療養において吸入器・吸引器を必要としている方
③主治医の同意を得ており、貸与する必要があると認められた方
豊島区での注意事項
「在宅難病患者医療機器貸与事業」を利用するにあたって、いくつか注意事項がありますので解説していきます。
- 障害者総合支援法など他の行政サービス(日常生活用具給付事業など)の利用が優先となります。他の事業により機器を取得できる方は、原則として対象外となりますので事前に確認しましょう。
- 貸与を受けた医療機器を損傷またはなくしてしまった場合は、原状回復(元通りになるため)に必要な費用を自己負担しなければなりません。
※ただし、天災(地震や台風、大雪など自然による被害)やその他やむを得ない事情によるものと知事が認めた場合は、その限りではありません。 - 医療機器を第三者に貸してはいけません。
- 貸与期間を経過した時、または貸与期間満了前に医療機器が不要になった時は、速やかに返却しなければなりません。
貸与を受けた方が、もしも注意事項を遵守できなかった場合、医療機器の返却や損害賠償が求められますので、くれぐれも注意して大切に扱ってください。
豊島区での制度利用の窓口
豊島区にお住まいの在宅難病患者さんが申請できる窓口は以下の2つです。
● 池袋保健所・健康推進課
住所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-42-16
利用時間:平日午前8:00~17:00
休館日:土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:03-3987-4172
● 長崎健康相談所
住所:〒171-0051 東京都豊島区長崎3-6-24
利用時間:平日午前8:00~17:00
休館日:土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:03-3957-1191
※駐車場はありません。
豊島区での申請方法
豊島区での申請に必要な書類は以下の通りです。
- 医療機器貸与申請書
- 主治医の指示書
- 難病医療券の写し(お持ちの方)
- 診断書(東京都難病医療費助成制度様式)※難病医療券をお持ちでない方
上記の書類を指定の窓口に提出・申請します。
その後知事が審査し、必要であると認めた場合は「貸与決定通知書」、認められなかった場合は「貸与非決定通知書」を通して申請者に通知されます。
定められた貸与期間の終了後、さらに延長を希望する場合には、更新の申請をしてください。
また、患者さんの病状変化やその他の理由により、貸与中の医療機器の変更や追加を必要とする場合には、
- 変更等申請書
- 主治医の指示書
- 貸与決定通知書
を添付して申請することができます。
まとめ
「在宅難病患者医療機器貸与事業」は、対象の方に吸入器・吸引器の貸し出しをしてくれる制度です。
無料で貸し出しをしてくれますが、大事な医療機器ですので。注意事項もあります。
貸与を受けたら大切に扱いましょう。
ただ、貸し出しをしてもらうためには、条件や窓口を通した申請が必要です。
制度についてもっと詳しく知りたい方は、池袋保健所・健康推進課もしくは長崎健康相談所の窓口に相談してみてください。
参考文献
https://www.city.toshima.lg.jp/220/documents/r5nanbyo-service.pdf
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/service/zaitaku/kikitaiyo
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/shinsa04030502