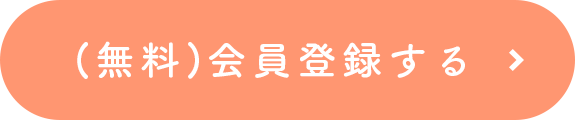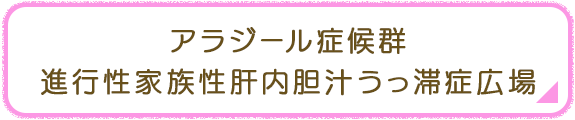近藤 宏樹 先生 インタビュー

近畿大学奈良病院
近藤 宏樹(こんどう ひろき) 先生
2018年04月 - 現在 近畿大学奈良病院小児科准教授
2016年04月 - 2018年03月 近畿大学医学部奈良病院小児科講師
2010年01月 - 2015年08月 大阪大学大学院医学系研究科小児科学助教
2003年04月 - 2009年12月 大阪府立母子保健総合医療センター研究所・環境影響部門主任研究員
「心が通う医療を届けたい」
病気を抱える子どもたちと日々向き合う医師たち。その背中には、診断・治療の技術だけでなく、子どもや家族を想う深いまなざしがあります。
今回は、小児の消化器・栄養・肝疾患の分野で長年ご活躍されてきた、近畿大学奈良病院 小児科の近藤宏樹先生にお話を伺いました。
診療におけるこだわりや、印象に残る出来事、ご家族への思いなど、先生の言葉の一つひとつから、医師としての誠実さと人間らしさがにじみ出るインタビューとなりました。
医師を志したきっかけ
「小さいころから、よくお腹を壊しては病院に行っていました。そんな経験があったからか、医師という仕事を“特別な存在”として見ていたんだと思います。」
近藤先生が“医師になろう”と強く決めたのは、進路を考える年齢になってから。
いざ進学先を決めるとき、「やっぱり医療の道に進みたい」と自然に思えたそうです。
「いろんな診療科がありますが、小児科は“自分が一番しっくりくる”と思えた場所でした。子どもは表情が豊かで、素直に反応してくれる。難しさもあるけれど、やりがいのある分野です。」
初期研修では、消化器や栄養の分野に関わる機会が多く、そのとき出会った指導医の先生が進路を大きく後押ししてくれました。
「とてもポジティブで、“どんなに大変でも楽しいよ”と常に笑顔で伝えてくれるような方でした。その姿に惹かれて、自分もこの道で頑張ってみようと思えました。」
医師になってから、今年で31年目を迎えた近藤先生。今なお変わらず、子どもたちと真摯に向き合い続けています。
忘れられない出来事と、医師としての信念
「もちろん、診断がうまくいって治療につながったときはうれしいです。でも、いちばん印象に残っているのは、やっぱり“助けてあげられなかった”患者さんたちなんです。」
かつては、今のように選択肢が豊富ではなかった時代。肝移植という方法が一般的ではなく、救命できないケースも多かったといいます。
「何もできずに見送るしかなかった…という経験が、何度もありました。」
そんな背景から、同僚である虫明先生を中心に肝移植チームが立ち上がり、徐々に治療の可能性が広がっていきました。
一方で、近藤先生は医師として大切にしている“もう一つの軸”を語ります。
「正しい情報を伝えることはもちろん大切です。でも、ただ“正しいこと”を言うだけでは、心には届かないんですよね。そこに“愛”や“思いやり”がなければ、人は救われない。」
たとえ最善を尽くしても、結果が伴わないこともあります。だからこそ、患者さんやご家族の気持ちに寄り添いながら、言葉を選び、心を通わせることを何より大切にしているそうです。
「外来診療でも、最後は必ず“笑って”帰ってもらうようにしています。」.....
※会員登録をいただくと、近藤先生のインタビュー記事の続きを読むことができます。
プロフィール設定の”関心のあるもの”より「インタビュー」「医師」をご選択ください。
※アラジール症候群・進行性家族性肝内胆汁うっ滞症についての情報がご覧いただけます。
患者さんご家族の体験談や医師のインタビュー、患者会の紹介を掲載しています。