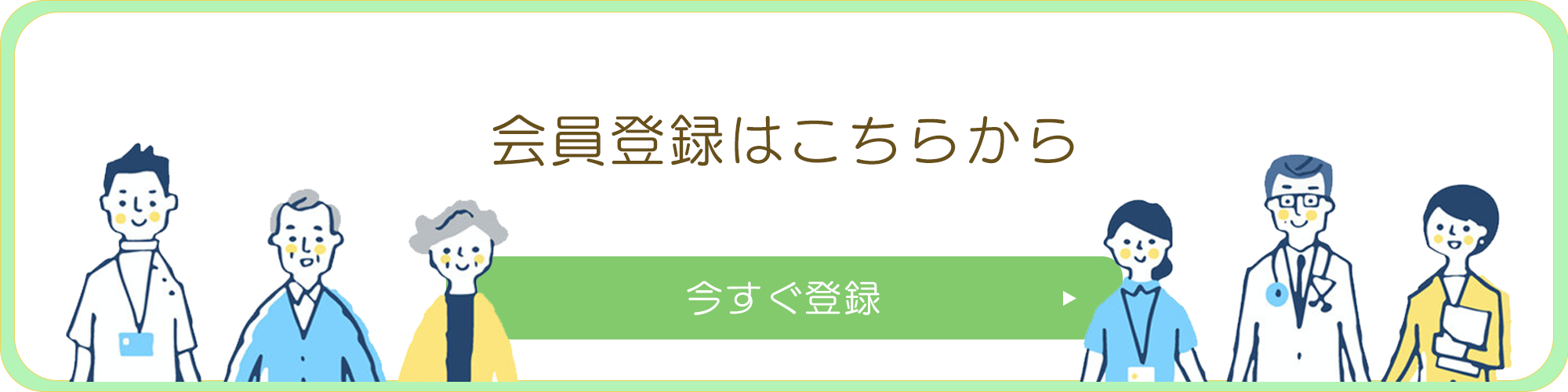“うちの子のやり方は?”――薬の飲ませ方の工夫あれこれ――
2025/10/15 公開
まずは相談から、そしてお子さんの気持ちも一緒に考えましょう
「どうやってこの薬、飲ませたらいいの?」
「粉砕してもいい?ゼリーに混ぜても大丈夫?」
そんな迷いや不安を抱えることは、決して珍しくありません。
そして――まず最初に大切なのは、“ひとりで判断せず、処方医や薬剤師に相談すること”です。
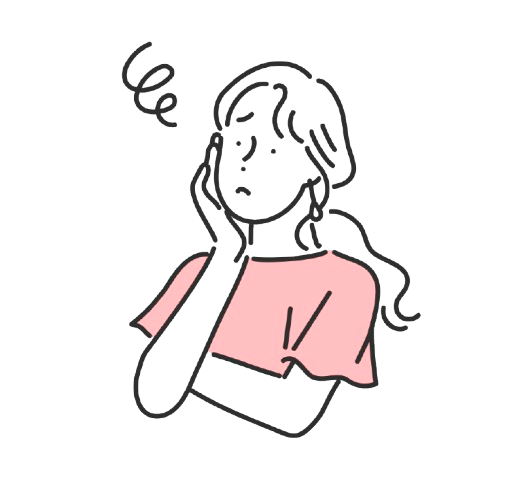
薬にはそれぞれ、形や性質に意味があります
薬には、形・溶け方・吸収のスピードなど、それぞれ設計された意味があります。
一見「ちょっとした工夫」でも、自己判断での粉砕や混合は効果や副作用に影響することがあります。
- コーティングを壊すと刺激が強くなる薬も
- 混ぜる食品によっては効果が落ちることも
- 経管投与では吸収場所やタイミングに注意
だからこそ、まずは専門職に相談を
※経管投与
お薬を口から服用することが困難な場合は、くすりを経鼻または胃ろうチューブから服用すること。
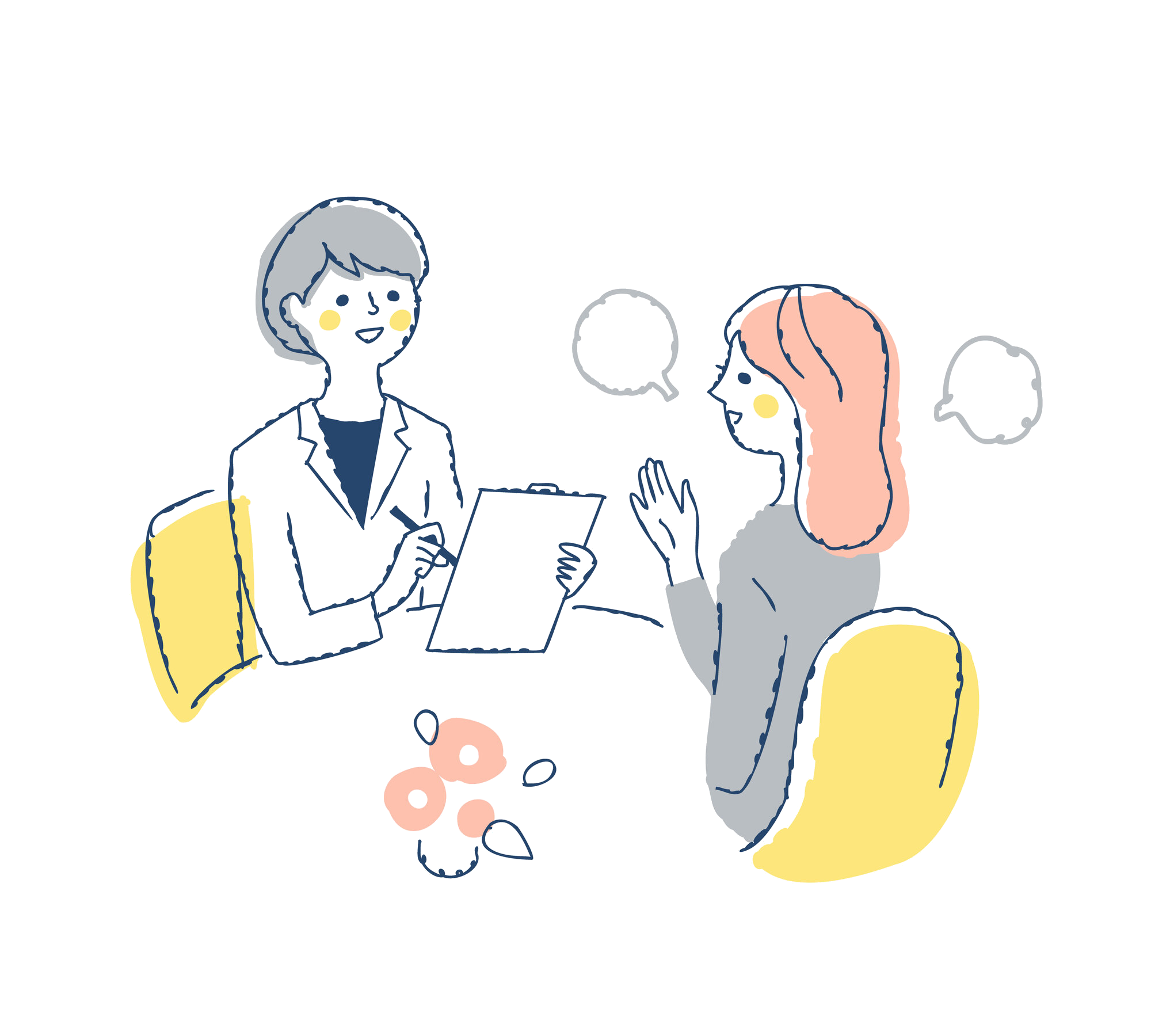
そしてもうひとつ、忘れてはいけないのは――
お子さんの気持ちに寄り添い、一緒に方法を探していくことです。
薬は毎日のこと。嫌がったり泣いたり、拒否することもあるでしょう。
それはお子さんなりの「ここはイヤだよ」というサインかもしれません。
どうか、その気持ちも尊重してあげてください。
飲めたときはたくさん褒めてあげましょう。
「すごいね!」「がんばったね!」という言葉が、明日への自信になります。
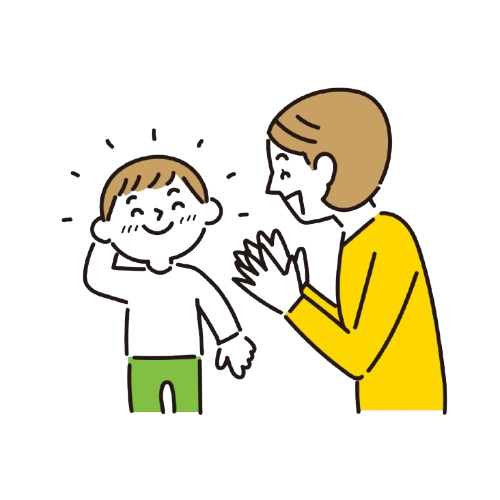
一緒に考える服薬の工夫
① 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)のお子さんの場合
粉薬はぬるま湯で溶かし、詰まりを防ぐために濾すなどの工夫を。
腸ろうの場合は薬の吸収に影響があるため、必ず専門職に相談を。
投薬後のフラッシュも忘れずに。
お子さんの状態や反応も見ながら、少しずつ工夫していきましょう。
▶参考サイト
簡易懸濁法による投薬の工夫(NPO法人PDN(Patient Doctors Network))
https://www.peg.or.jp/care/kendaku/index.html
② 嚥下障害・誤嚥リスクのあるお子さん
薬にとろみをつける際は、医療用とろみ剤(食品用より安定)を使用。
とろみの濃さは「薄い・中間・濃い」の3段階で、お子さんに合わせて調整。
シリコン製や柄の短いスプーン、角度が工夫されたスプーンなどもおすすめ。
苦い薬は、アイスクリームやゼリーに混ぜたり、甘味を追加して飲みやすく。
嫌がるときは、無理に飲ませず、成功体験を積み重ねることが大切です。
③ 神経・筋疾患などで姿勢保持が難しいお子さん
姿勢を整えて安全に飲めるよう工夫を。
嫌がる時は、好きな音楽や香り、ぬいぐるみなどで気分転換を。
服薬タイミングは食後・排泄後など、体調が安定しているときに設定しましょう。
長時間の服薬は複数回に分けて、嫌がる時は気分転換やタイミングを変えてみて
お子さんの反応をよく観察し、一緒に無理のないリズムをつくっていきましょう。
④ てんかん・代謝性疾患など服薬時間が重要なお子さん
アラームやスケジュールを使って確実に管理。
服薬が難しい場合は、散剤→シロップ→錠剤など剤形変更も可能か医師に相談も。
お子さんのペースに寄り添いながら、続けやすい方法を模索しましょう。
日々の記録をつけ、飲めなかった時の理由や時間も共有できると◎。
専門職に相談して、「ラクできる道」を探してもいい
保護者だけで頑張りすぎなくても大丈夫です。
薬剤師さんは、味や形状を変える処方の相談に乗ってくれる心強い存在。
また、訪問看護師さんは、投薬のタイミングやケアの導線を一緒に見直してくれることもあります。
「うまくいかない日」もある。そんな日も、前に進む一歩です
薬を飲むことは、とても大切なこと。
でも、ときにはうまくいかない日があるのも自然なことです。
無理に続けてお互いがつらくなってしまうより、
いったん気持ちを整えて、また次の一歩につなげられたら、それで十分です。
「思うようにいかなかった日」に、心が沈んでしまうこともあるかもしれません。
でも、それも親子で前に進むプロセスのひとつ。
あなたとお子さんのペースで、“うちの子なりのやり方”を一緒に見つけていけたら、それが何よりの正解です。
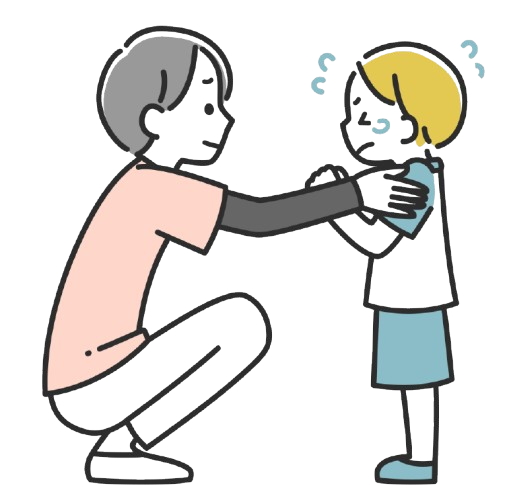
最後に
旅の前には、準備や心配ごとが尽きないものです。
でも、「家族みんなで同じ時間を過ごすこと」は、何よりもかけがえのない体験になるはずです。
医療的ケアが必要なお子さんも、
兄弟姉妹のみなさんも、
そして日々支えている大人たちも。
それぞれが、「これは自分のための旅だった」と感じられるような、そんな時間になりますように。
もし不安や迷いがあれば、ひとりで抱えず、ぜひ誰かに話してみてください。
私たちも、そんなときにそっと寄り添える存在でありたいと思っています。
楽しい旅のひとときが、たくさんの笑顔につながりますように。
参考サイト
https://www.jstage.jst.go.jp/article/faruawpsj/58/3/58_223/_article/-char/ja/
・子どもの薬(島根県薬剤師会)
おくすりQ&Aに子どもの薬にお薬の飲ませ方が説明されています。
・子どものくすりの飲ませ方(さいたま薬剤師会)
https://saitama-shiyaku.or.jp/knowledge/children/