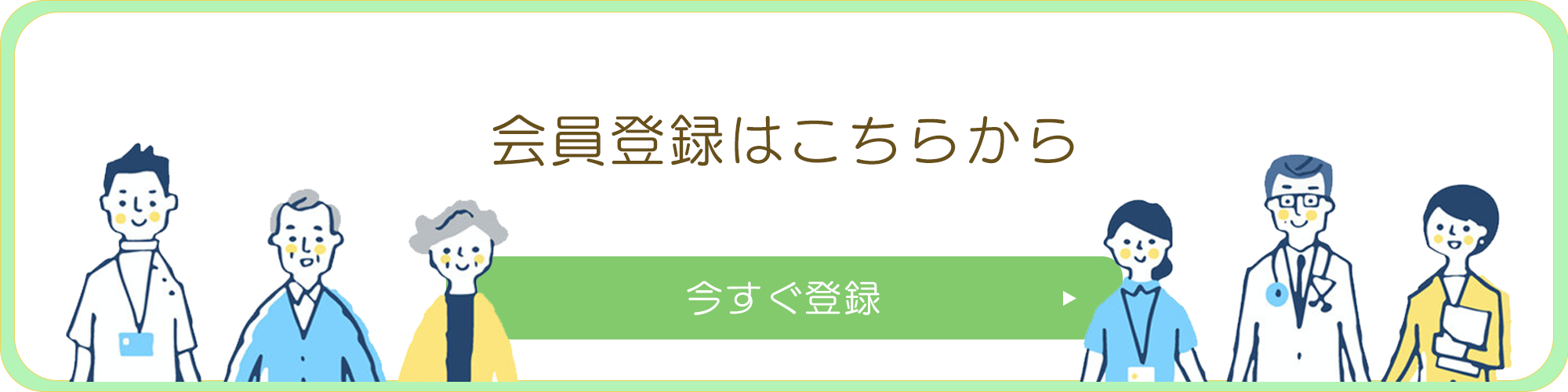「食べる」ことが、選べることに
──嚥下障害のある子どもたちと、インクルーシブな食の未来
2025/10/21 公開
「今日はどれを食べようか」
そんな、当たり前のように思える問いが、嚥下障害のある子どもたちにとっては、
日常の中でとても特別で、時に難しいものです。
食事は、栄養補給のためだけの行為ではありません。
「おいしいね」と笑い合うこと、「どれにしよう」と迷うこと、「また食べたい」と感じること
──それらすべてが、子どもの成長と心の豊かさを育む大切な体験です。

選べるってうれしい!
嚥下障害の子どもたちの“食べる楽しさ”を広げる工夫
● メニューの選択肢が極端に少ない → “選べる”食事を少しずつ増やそう
嚥下障害がある子どもたちの「食事のレパートリーや味に飽きてしまう」問題は
とても深刻です。
「食べられるもの」が限られているからこそ、同じような見た目・味・食感が繰り返され、食事が“義務”や“作業”のように感じられてしまうこともあります。
以下に、実際の現場で活用されている・または家庭で試しやすい 「飽きへの工夫」 を紹介します。
■飽きを防ぐための工夫アイデア■
1. 食材の変化より“味つけ”や“香り”を変える
嚥下形態が変えられなくても、味や香りのバリエーションは出せます。
例:
- かぼちゃペースト → シナモンやバター風味を追加
- 白身魚のミキサー食 → 柚子胡椒、味噌だれ、トマトソース風など
◎ポイント:香りの変化が「食欲」を刺激しやすいです!
2. “重ねる”ことで味に深みを出す(多層ゼリーなど)
•単一の味ではなく、2〜3層構造のゼリーにしてみると、食べていて変化を感じられます。
例:
- だしゼリー+具材ゼリー+とろみソースの三層構造
- デザートなら、ヨーグルトゼリー+果汁ゼリー
◎ポイント:「変化を感じる」=「楽しさ」に近づけるコツ
3. 色彩・盛りつけで“目からの刺激”をプラス
嚥下調整食はどうしても色が地味になりがちですが、野菜パウダーやピューレで色を加えると華やかになります。
例:
- 紫芋、ほうれん草、かぼちゃ、にんじんなどのピューレで彩り
- かわいい型抜きゼリーや、ソースのドット絵風盛り付けなど
◎ポイント:見た目の変化が「また食べたい」につながることも
4. イベント食・記念日メニューを導入する
毎日の食事はシンプルでも、季節や行事のときだけ少し特別にすることで、ワクワク感を生み出せます。
例:
- ひな祭り:三色ゼリー(白・ピンク・緑)
- ハロウィン:かぼちゃプリン風嚥下ゼリー
- 誕生日:ゼリーケーキ風の重ね盛り
◎ポイント:「今日は特別!」と感じられるだけで食事の意味が変わる
5. 家族と“見た目をそろえる”工夫
同じメニューを食べることが難しくても、同じ色合い・盛りつけの「似た見た目」で提供することで孤立感を減らせます。
例:
- 家族が食べるハンバーグと、嚥下対応ハンバーグゼリーを同じ皿に盛り付け
- トレイやカトラリーを揃えて「みんなと一緒」を演出
6. 市販品の活用とアレンジ
最近では「おいしさにこだわった嚥下調整食」も増えています。
味付きゼリー・とろみスープ・レトルト嚥下ミールなどを味変アイテムとしてストックしておくのも手です。
例:
- 市販のスープゼリーを数種買って「選ばせる」楽しさを提供
- 同じ食材でも違う調理済パッケージを使うと変化を演出できる
◎ポイント:「選べること」がモチベーションにつながる
7. 食事以外の楽しみとセットにする
「食べること」がストレスになってしまった子には、好きなアニメの食器やお気に入りの絵本のテーマメニューなど、食事+αの楽しみをつけてみる工夫も効果的です。
8.番外編:無理せず続けるために大切なこと
- 無理に量を増やす
- 急に味を変えすぎる
- 「食べなきゃだめ!」と叱る
これらは食べる意欲をさらに削いでしまう原因になります。
本人の様子をよく観察して、ゆっくりペースで進めましょう。
<参考になるサイト>
嚥下調整食動画(一般社団法人 日本接触嚥下リハビリテーション学会)
https://www.jsdr.or.jp/doc/food_movie/
米粉でやさしい嚥下食(国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院リハビリテーション科)
米粉でやさしい食生活(米粉活用研究会)



伝わらない、知られていない「ニーズ」
嚥下障害について正しく理解している飲食関係者はまだ少なく、
外食時に「その程度の制限なら大丈夫ですよ」と軽く言われてしまうことも少なくありません。
メニューに嚥下レベルの表示がある飲食店もほぼ皆無で、対応をお願いするにも、
どこまで伝えればいいのかが分からず、外食を諦める家族もいます。
「こういう食事なら安心です」「これがあると助かります」
——そんな小さな伝え方でも、きっと誰かの気づきにつながります。
全部を一度に話そうとしなくて大丈夫。伝えられるときに、伝えられる範囲でいい。
声をあげることで、「あ、そういうニーズがあるんだ」と気づいてくれる人が必ずいます。
それに、無理に一人で抱えなくてもいいんです。同じような経験をしている人たちと情報を共有したり、SNSや地域のサポート団体を頼ったりするのも、
前に進む一歩です。
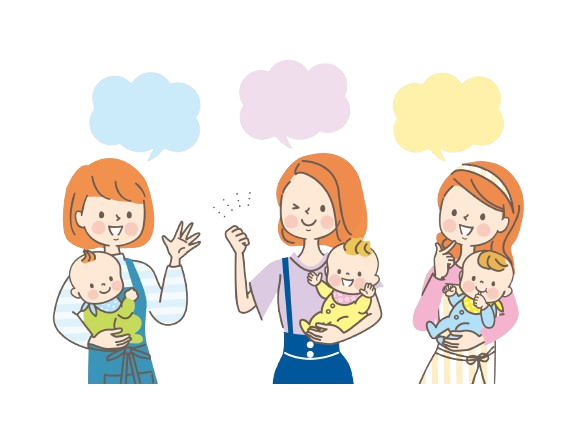
買える場所、食べられる場がない
市販の嚥下調整食品は、ドラッグストアやスーパーでは手に入りにくく、ネット注文でも送料が高くつくことが多いです。
また、学校や保育園、外出先の施設でも「持ち込み」対応が必要になるケースが多く、“みんなと同じ場所で、
同じように食べる”という体験が難しい現実があります。
たとえば、地域のドラッグストアやスーパーに「こういう商品を置いてほしい」とリクエストしてみること。
地元の小売店が声に応えてくれるケースもあるかもしれません。
また、同じ悩みを持つ家族同士でつながると、「ここで買えるよ」「この園は対応してくれたよ」など、生きた情報が手に入ります。
1人で全部抱えなくても、経験を分かち合うことで、私たちの選択肢はもっと広がるはずです。
“みんなと同じように食べる”ことは、あきらめなくていい。小さなアクションが、少しずつ環境を変えていく。その力を、私たちはきっと持っています。
専用食品の高額さ
嚥下食は、市販食品の中でも比較的高額です。1食あたりのコストは、通常のレトルト食品の2倍〜3倍に達することも。
また、福祉制度による補助も少なく、家庭の経済的な負担が非常に大きいという課題もあります。
たとえば、自治体に補助制度の導入や改善を求める声を届けたり、医療や福祉の現場と連携して、制度の隙間にある「食のニーズ」を可視化することもひとつの方法です。すぐに変わらないかもしれませんが、声をあげる人が増えることで、行政や企業の動きも変わっていくはずです。
また、家庭での工夫や情報共有も力になります。たとえば、身近な食材や市販品を使って“やわらか食”を手作りしている方も多く、そのレシピやコツを共有し合うことで、コストを抑えながら安全な食事を続けることができます。
「必要なものを、必要なだけ、無理なく手に入れられる社会にしたい」——それはきっと、私たちだけの願いではないはず。
だからこそ、声をあげ、つながり、諦めずに問い続けていきたいですね。
心理的・社会的な“壁”の存在
「自分だけ違う」「わがままだと思われたくない」
周囲との違いを強く意識する子どもにとって、「みんなと同じように食べられない」ことは、心理的な孤立感を生みやすくなります。
- 「私だけ別のごはん」
- 「変な食べ物を食べていると思われるかも」
- 「同じように楽しめない」
また、保護者や支援者も「配慮をお願いすること」自体が負担やストレスになりがちです。
じゃあ、この“心の壁”にはどう向き合えばいいのでしょうか?
「なんで私だけ?」「変だと思われたくない」——こう感じてしまうのは、子どもだからではなく、とても自然なことだと思います。
そして、大人である私たちもまた、「お願いするのが申し訳ない」「また迷惑をかけるのでは」と気を使いすぎてしまい、
外食やイベントを避けたくなることもあるでしょう。
でも、だからこそ、ひとつずつ“当たり前”を増やしていけたらと思うのです。
たとえば、食事の場で特別視されないように、持ち込みを前提とした自然な配慮の仕方を、先生や支援者と一緒に考えること。
行事のときに事前に相談し、「みんなと同じ雰囲気で楽しめるようにしたい」と伝えてみること。相手に“お願い”ではなく“協力”として伝えるだけで、
受け止め方が変わることもあります。
そして何より、子どもたち自身が「違う=悪いことじゃない」と思えるような、周囲の声かけや環境づくりもとても大切です。
保育園や学校の中で、食の多様性や配慮について話す機会をつくることで、子ども同士の理解も少しずつ深まっていきます。
「みんなと同じ」じゃなくても、「みんなと一緒に」楽しめる。そんな経験が積み重なれば、
子どもも大人も、少しずつ心の壁を越えていけるのではないでしょうか。

医療的配慮と“美味しさ”のバランス
安全性を優先しすぎると、「食べられるけど美味しくない」というジレンマが生まれます。
一方で、美味しさや見た目を重視しすぎると、誤嚥・窒息といったリスクが高まる可能性もあるため、提供側も慎重にならざるを得ません。
このバランスをとるためには、医療・福祉・栄養・調理の専門家たちの連携が不可欠です。
2025年の今、嚥下食をめぐる支援の現状
2025年の今も、食べる力に課題を抱える子どもたちにとって、安全に、そして楽しく「食べる」ことを支える環境は、まだ十分とはいえません。
たとえば、医療的ケアが必要な子ども、発達に特性がある子、口腔や嚥下機能の発達がゆっくりな子などは、とろみをつけた食事や、柔らかく形を整えた“嚥下食”が必要です。
でも、こうした食事を家庭で用意するのは負担が大きく、保育園や学校での対応も、現場によって差があります。
一部の自治体では、特別支援学校や通園施設などで専門職(言語聴覚士、管理栄養士)がかかわる体制づくりが進んでいます。
また、栄養補助食品やとろみ剤などの提供に助成を設けている市町村も出てきています。
けれど、全国的にはまだまだ不十分です。
「給食で食べられるものが少ない」「誤嚥の不安から食べる楽しさを感じられない」「支援がなくて、食事の時間がつらい」といった声も、多く聞かれます。
子どもにとって「食べること」は、命をつなぐだけでなく、喜びや自立、社会参加の一歩でもあります。
今後は、医療・保育・教育・家庭がもっと連携し、子ども一人ひとりの“食べる力”を支える仕組みづくりが必要です。安心して、楽しく、そしてみんなと同じように「いただきます」と言える毎日を目指していくことが大切です。
<参考になるサイト>
新宿ごっくんプロジェクト ~摂食嚥下機能支援~(新宿区)
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/kenko01_001089.html
まとめ
制限の中でも“選べる・楽しい”をあきらめない。
「食べられるものが少ない=楽しめない」ではありません。
ほんの少しの工夫や視点の切り替えで、子どもたちの表情は変わり、「食べること」そのものが前向きな体験になります。
小さな選択肢、見た目の工夫、香りの刺激。
それぞれはささいなことでも、重ねることで、「自分のためのごはん」という実感を持てるようになります。
「安全」も「楽しさ」も、どちらも大切にできるように。
一歩ずつ、インクルーシブな“おいしい未来”を広げていきましょう。
参考になるサイト
関連お役立ち情報サイト
https://www.soup-stock-tokyo.co.jp/project/soshaku/
スープストックトーキョーは、創業当時から「Soup for all!」という考え方のもと、食のバリアフリー対応を推進しており、その一環として「食べやすさ配慮食」の提供を行っています。
「食べやすさ配慮食」は、年齢を重ねた方、障がいがある方、歯の治療中でかたいものを食べられない方など、さまざまな理由で「食べる力」に不安がある方に寄り添う食事です。あらゆる方が一緒に一つの食卓を囲み「おいしい」を分かち合えるように、という想いが込められています。