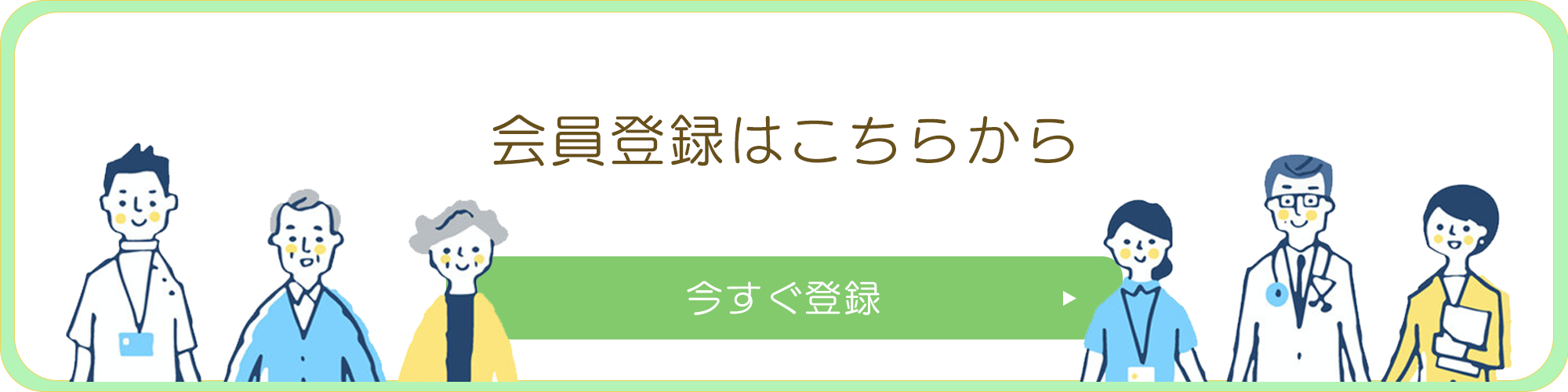災害時に障害のある方が安全に行動するために
2025/7/25 公開
災害が起きたとき、障害のある方が安心して避難するには、日ごろの備えと周囲の理解・協力がとても大切です。以下の4つのポイントを参考にしましょう。
①持ち物(非常持ち出し袋の中身)
②普段からの備え
③災害が起きたら
④支援する方へ
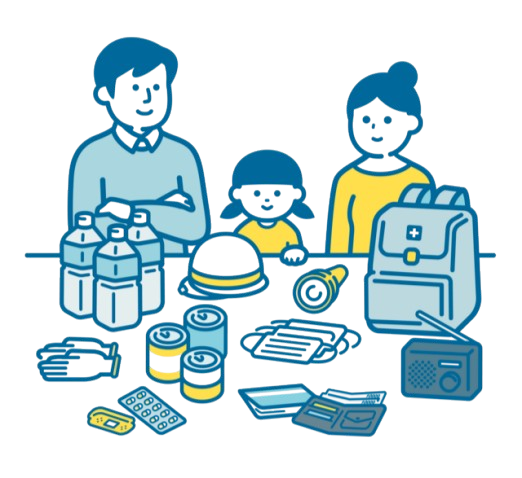
持ち物(非常持ち出し袋の中身)
災害時には、必要なものをすぐに持ち出せるよう、非常持ち出し袋を準備しておきましょう。
- 常備薬とお薬手帳、飲むときに必要な補助道具。
- 障害者手帳のコピー。
- 助けを呼ぶ笛や音が出るブザー。
- ヘルプカード(連絡先メモ、名前、住所、電話番号、困ったときに助けてほしいこと)。
- 補聴器、電池、眼鏡、白杖、装具など。
- 落ち着けるおもちゃや本など。
- 筆談用ノートとペン。
- 食事・水(アレルギーや嚥下対応のもの)、補助食。
- バッテリー。
- おむつ、吸引器など個別に必要なケア用品、床ずれ対策。
普段からの備え
災害に備えるためには、日ごろの準備と情報の共有が大切です。
- 緊急時に対応してくれる医療機関、相談窓口を調べておく。
- 支援者が被災などして不在の場合の対応を家族や周囲の方と相談。
- 災害時の対応を主治医と相談(薬の保管法、治療食、薬が飲めなかったときの対応)。
- 「自分に必要な配慮」を書いたカードを用意する。
- ヘルプカードを身に着けておく。
- 避難訓練に参加する(できれば地域と連携して)。避難経路(複数)、避難場所の確認する。
- 自治体の避難行動要支援者名簿(※1)に登録。
- (知的障害のある方)名前、住所、電話番号を書いたものを身に着けたり、服に縫い付けたりする。
- (車椅子の方)バリアフリーがなく避難所が使えない場合は、自治体に連絡して相談しておく。
※1避難行動要支援者名簿
各自治体が作成した災害時に「助けが必要な人」をまとめたリストです。
自治体や消防署、警察が災害時に支援しやすくなります。
<防災情報ページ(内閣府)>
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/yoshiensha.html
災害が起きたら
災害が発生したときは、落ち着いて安全を確保し、支援を受けながら避難しましょう。
- 補助具、非常用持ち出し袋を持ち出し、周囲に支援を頼む。
- 決めておいた支援者に連絡をとる。
- ヘルプカードや障害者手帳を提示して支援を求める。
- 動けない場合は笛やブザー、大声で助けを求める。
- (知的障害のある方)フラッシュバックを起こす危険のある時はニュースに注意する。
支援する方へ
障害のある方を支援する方も、以下のような心がけをしておくと安心です。
- 普段から支援対象の方と連絡をとっておく。
- どのようなサポートが必要か、事前に確認しておく。
- 声かけはゆっくり、丁寧に。いきなり手を引かず、「○○さん、△△しますね」と声をかけてから(視覚・聴覚障害の場合は特に配慮を)。
- 情報が入りづらい人には、文字や図で説明する配慮も考慮する。
おわりに
障害のある方も、支援する人も、災害時に慌てず行動できるよう、日ごろからの話し合いと準備がとても大切です。
地域の中で助け合い、誰もが安心して避難できるようにしていきましょう。
参考サイト
<災害時障害者のためのサイト(NHK)>
https://www.nhk.or.jp/bousai/shougaisha/index.html?tab=disabled#Main
<ヘルプカードのテンプレートを配布している自治体の一例>
千葉市
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/rikaisokushin/herupumaku.html
小山市
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/shougai/shien/page003817.html
<緊急時に対応してくれる医療機関、相談窓口の一例>
自治体ごとに相談窓口を問い合わせてみましょう。
例)神奈川県災害派遣福祉チーム(DWAT)