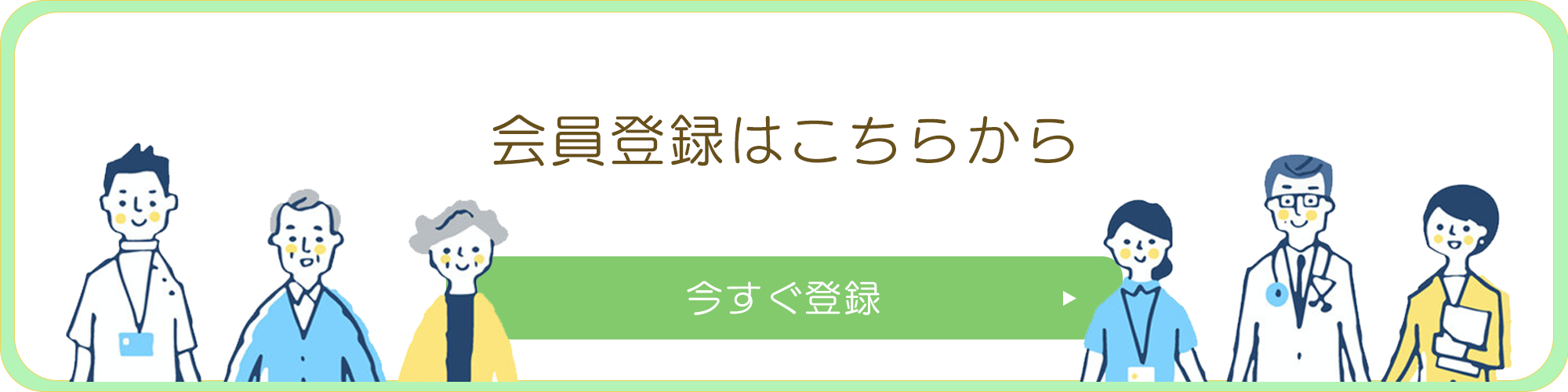「できない」じゃなくて「できる」を見つける。難病の子どもとスポーツの話
2025/9/17 公開
1. はじめに
こんにちは。
この記事を読んでくださっている方の中には、
「病気のある子が運動しても大丈夫なの?」
「うちの子にできることなんてあるのかな…」
と感じていらっしゃる方もいるかもしれません。
たしかに、難病や慢性の病気があると、体を動かすことに不安を感じるのは当然のことです。
無理はできないし、疲れすぎてしまったり、体調を崩してしまうことも心配ですよね。
でも実は、「できる形」で無理なく運動やスポーツに取り組むことで、身体だけでなく、心や日々の生活にも良い変化が生まれることがあるんです。
2.運動・スポーツが難病の子に与えるメリット
難病のお子さんでも、できる範囲で体を動かすことで、さまざまな良いことがあります。
1. 体の面での良い変化
まず、筋力や体力を維持することができます。病気によっては動くことが制限されてしまう場合もありますが、だからこそ無理のない範囲で体を使うことで、関節のかたさを防いだり、筋力の低下をゆるやかにしたりすることが期待できます。
2. 心と心のつながり
心の面でも大きな効果があります。体を動かすことで気分が晴れたり、「自分にもできた」という達成感を味わったりすることができます。
さらに、運動を通してお友だちやまわりの人と関わる機会が増えることで、学校生活や地域でのつながりも感じやすくなるかもしれません。
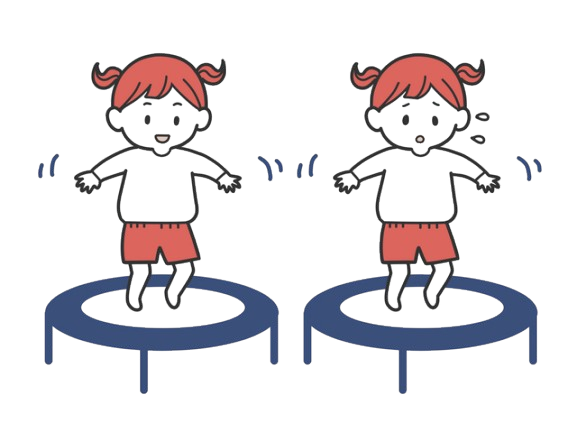
3.運動を始める前に考えるべきこと
とはいえ、「うちの子にとってどんな運動が安全なのか、わからない…」という方も多いと思います。
運動を始める前には、主治医の先生と相談することがとても大切です。病気の種類や状態によっては、避けた方がいい動きや、気をつけるポイントがあるかもしれません。
また、学校や療育の先生、理学療法士さんなど、お子さんのことをよく知っている支援者と一緒に考えることで、より安全で無理のない方法を見つけることができます。
運動は「がんばらせるもの」ではなく、「本人が楽しくできること」が一番です。
お子さんの体調や気持ちに合わせて、少しずつ始めていくことが大切です。
運動は「がんばらせるもの」ではなく、「本人が楽しくできること」が一番です。
お子さんの体調や気持ちに合わせて、少しずつ始めていくことが大切です。
4.実際にできる運動・スポーツの例
―「やってみたい」を大切にする、小さなスタート。
ここでは、難病のお子さんが安心して体を動かすためのヒントを、いくつかの例とともにご紹介します。
- ストレッチや簡単なヨガ:おうちでできて、筋肉や関節をやわらかく保てます。
- イスに座ってできる体操:上半身だけでも動かせればOK。
- 車いすスポーツ:バスケットボールやテニスなど、専門チームや教室もあります。
- お散歩やゆるやかな外遊び:外の空気を吸って、ゆっくり歩くことでも十分な運動になります。
「こんなことでもいいの?」と思うような、小さな動きでも、それは立派な運動です。
できる範囲で、楽しく取り組めることを一緒に見つけていきましょう。

<参考サイト>
作業療法士ママが教える!子どもの発達を伸ばす「おうち遊び」10選|年齢別アイデア&OT流声かけ例つき【家にあるものでOK】(はるかママ)
https://mama-haruka.com/ot-mom-play-at-home?utm_source=chatgpt.com
5.難病のあるお子さんが競技スポーツをしたいとき、どうすればいい?
パラスポーツやユニファイドスポーツなど、「共に楽しめる競技」を探してみましょう。
たとえば、病気や障害があっても、まわりのみんなといっしょに楽しめるように工夫されたスポーツの場があります。
■ユニファイドスポーツってどんなもの?
ユニファイドスポーツは、知的障害のある人(アスリート)とない人(パートナー)がペアになり、同じチームでプレーするスポーツプログラムです。これにより、障害の有無に関係なく、みんなが一緒に楽しむことができる環境が作られます。
障害の有無に関わらず、同じチームでプレーする競技形式です。
サッカー・バスケ・バレーボールなど、多くの競技で実施されています。
ユニファイドスポーツの情報は、スペシャルオリンピックス日本(SON)公式サイトや地域のスポーツ協会や支援団体のウェブサイトで探すことができます。
<参考サイト>
知的障害のある人の「ために」ではなく、「ともに」スポーツを楽しむ(スペシャルオリンピックス)
https://www.son.or.jp/business/unified/
■パラスポーツとは?
パラスポーツは、障害のある方もない方も一緒に楽しめるスポーツです。例えば、車いすテニスやボッチャ、パラダンスなどがあります。これらのスポーツは、障害の種類や程度に関係なく、誰もが楽しめるように工夫されています。
どこで参加できるの?
1. 地域のスポーツセンターや福祉施設
多くの地域で、障害のある方を対象としたスポーツ教室や体験会が開催されています。例えば、東京都では、障害のある方もない方も一緒に楽しめるパラスポーツイベントが開催されています。
<参考サイト>
TOKYOパラスポーツ・ナビ
https://www.tokyo-parasports-navi.metro.tokyo.lg.jp/
障害者スポーツができる場を探す(東京都)
https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/suru/basyo_forthedisabled.html
2. パラスポーツ協会や団体
全国には、パラスポーツの普及や支援を行っている団体があります。
■競技そのものにこだわらなくても、「競技に関わる」参加方法も
難病の状況によっては、「プレイヤーとして長時間動く」ことが難しい場合もあります。
そんなときも、たとえば:
ボールを投げるだけでもOK
ゴールキーパー・キャッチャー役など限定的な役割
チームのスコア係、応援係、作戦係として参加
など、「競技を一緒に楽しむ」形はたくさんあります。
「一緒にプレーできた」経験が、お子さんの大きな自信や思い出になります。
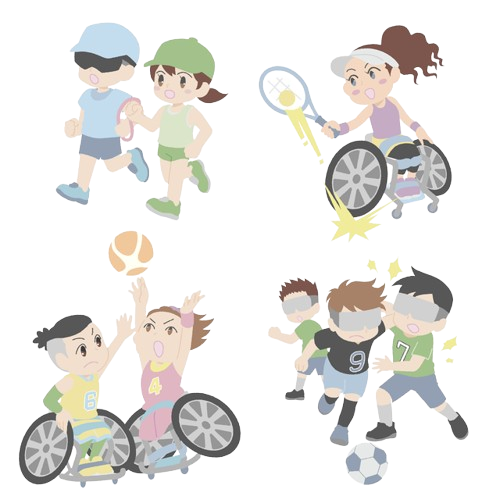
6.家族や周囲の支援体制
お子さんが安心して運動できるようにするには、まわりの支えがとても大切です。
ご家族はもちろん、学校の先生や療育のスタッフ、医療者、そして運動の指導に関わる方たちが、お子さんの状態や特性を理解し、寄り添ってサポートすることが求められます。
ご家族自身も、無理に「やらせなきゃ」と思わなくて大丈夫です。
まずは「できることを一緒に楽しんでみよう」という気持ちがあれば、十分です。
7.地域や社会の取り組み・制度
最近では、病気や障害のある子どもたちが参加できるスポーツ教室や体験イベントが増えてきています。
また、医療的ケアが必要な子ども向けの運動支援プログラムや、特別支援学校での体育活動などもあります。
自治体やNPO法人、病院などが行っている活動もあるので、「うちの地域にもあるかな?」と調べてみると、思わぬ出会いや選択肢が見つかるかもしれません。
<参考サイト>
障がい者スポーツ教室案内(渋谷区)
障害者スポーツセンターとは?(笹川スポーツ財団)
https://www.ssf.or.jp/thinktank/disabled/sports_facility.html?utm_source=chatgpt.com
8.おわりに
難病のある子どもたちにとって、運動やスポーツは、「無理をするもの」ではなく、「楽しみや生きる力を育むもの」です。
すべての子に、同じようなことができるわけではありません。
でも、「その子に合ったペースややり方」で、体を動かすことはきっと可能です。
お子さんが「できた!」「楽しかった!」と笑顔になれるような、そんな一歩を一緒に見つけていけたら嬉しいです。