〈患者会〉HPP HOPEインタビュー 前編
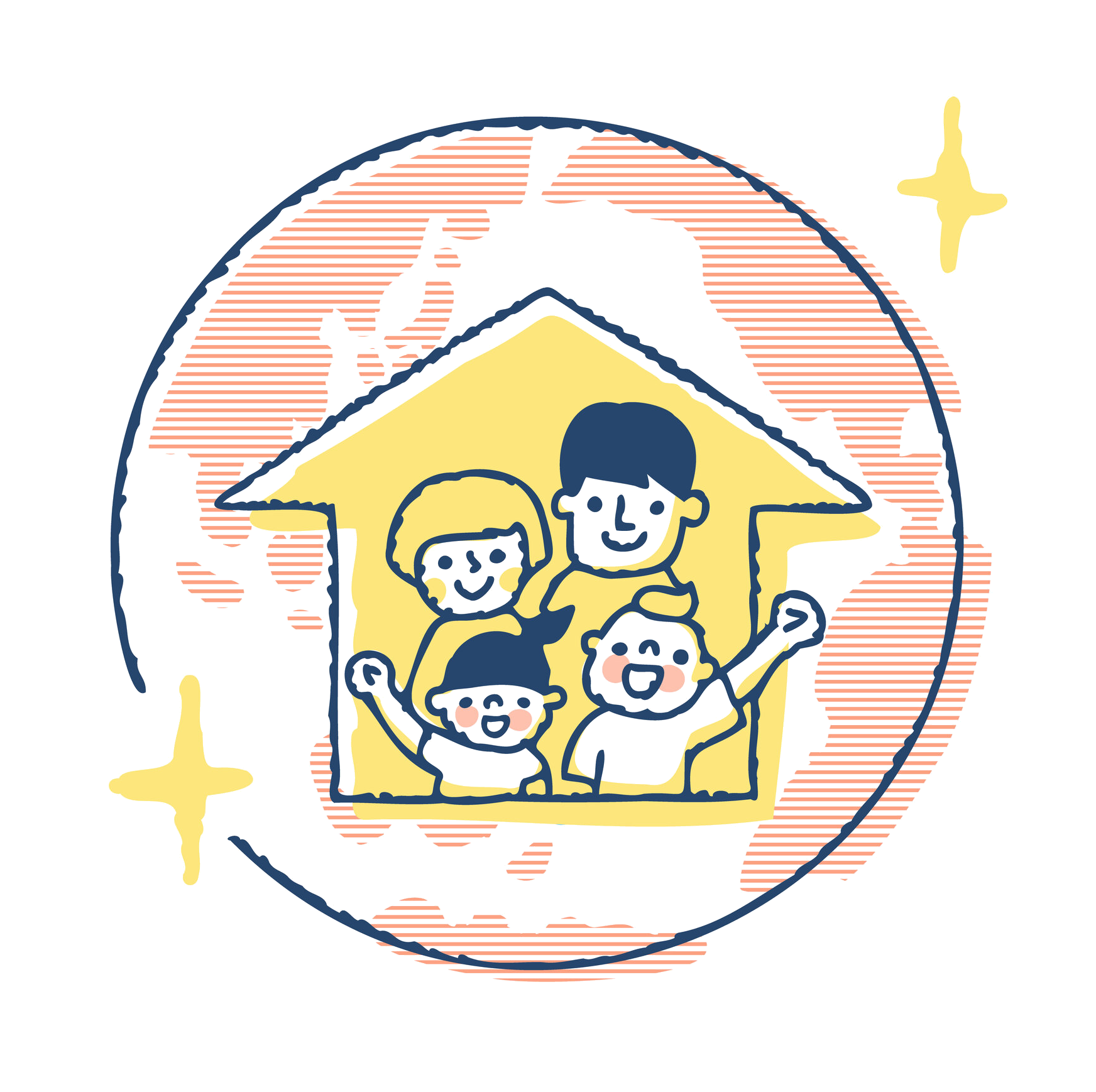
患者会
HPP HOPE(小野澤 様・原 様)
□ 2008年10月、6家族で患者会 を設立
「つながる」をテーマに患者同士の交流の場、海外などを含めた低ホスファターゼ症に関する最新情報の提供、
他の患者さんの治療経過や身体の成長記録などを確認できる治療経過可視化システムの開発/運用などを
活動として行っております
国の指定難病の一つに数えられる、骨の遺伝性疾患「低ホスファターゼ症」。
HPPと呼ばれるこの病気は、体内で作られる酵素アルカリホスファターゼの異常によって骨の石灰化が阻害され、
骨の強度が弱くなり、骨折や骨痛、歯の欠損など様々な骨の症状を引き起こすという特徴があります。
2015年に国内で治療薬が承認され、重症の場合でも救命が可能になってきているものの、現時点で根治は困難。その治療体制にも課題が残されています。
このような状況に一石を投じ、低ホスファターゼ症の患者やその家族の拠り所となって積極的に活動を展開しているのが、NPO法人「HPP HOPE」です。
低ホスファターゼ症の患者会として2008年に創設され、患者同士や家族、医師、製薬会社、行政との橋渡し役を担い、病気に関する啓蒙活動を継続。
2024年には、NPO法人化を果たしました。
今回は、HPP HOPEの創設者である原さんと、現代表を務める小野澤さんに、これまでの足跡や現在の取り組み、今後の展望について詳しくお話を伺いました。
※以下、敬称略
※以下、低ホスファターゼ症を「HPP」と記載
患者会の入会
Q:まずは、HPP HOPEの会員の方が、どのような経緯で入会に至ったのか、お聞かせいただけますか。
(原さん)
入口としては、生まれる前に病院でHPPであると診断されて入会するケースと、生まれた後に症状が出てきて入会を希望されるケースが多いです。
また、最近は大人の方の患者さんの入会が増えています。最近は製薬会社のメディアなど色々な情報があり、それを見た方から「もしかしたら私はHPPじゃないだろうか」「病院はどこにあるでしょうか」といった問い合わせがあるので、それに対してアドバイスさせてもらっています。
また、病院を受診したらHPPであることが分かり、それがきっかけで入会したという方もいます。
Q:やはりメディアの力があると考えられますが、HPPの患者会の存在は、病院でも周知されているのでしょうか。
(原さん)
そうですね、どこまで周知されているか分からないのですが、昔と比べるとその認知度は間違いなく高まっており、先生からご紹介いただいたケースもあると聞いています。
歯科医の先生に対するHPPの患者会の認知度は高いですが、成人の患者さんを診ている先生方に対しては認知度が低いように感じます。だから、大人の方は自分で患者会を探してきた、という方が多い印象です............
※会員登録をいただくと、HPP HOPEのインタビュー記事の続きを読むことができます。
プロフィール設定の”関心のあるもの”より「患者団体」「インタビュー」をご選択ください。




