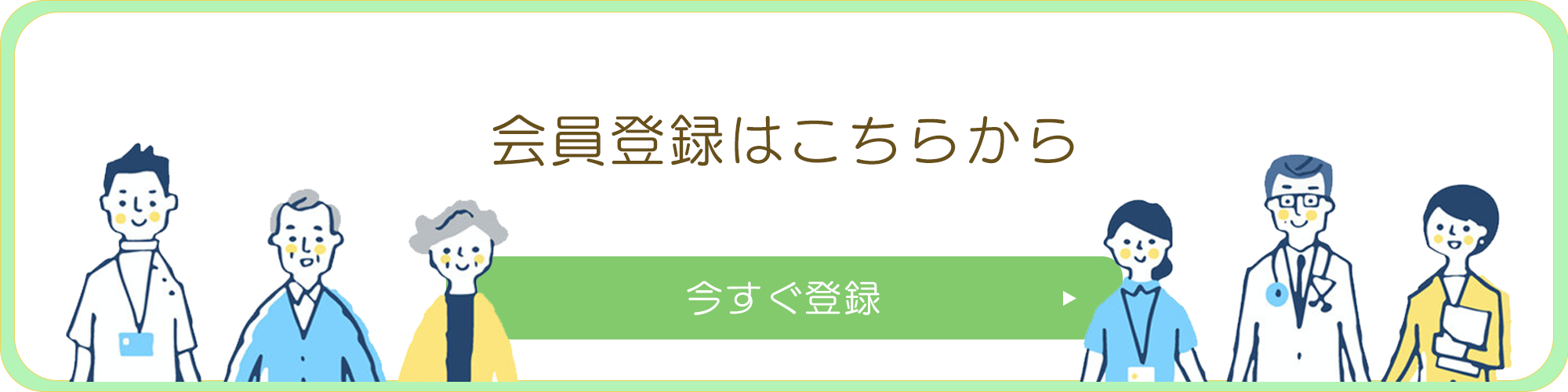「“学ぶ”って、わが子にとってどういうこと?
――難病とともに歩む子どもの就学を考える」
幼稚園・保育園期②(シリーズ掲載)2025/11/07公開
幼稚園・保育園期:最初の壁と親の準備
医療的ケアや難病のある子どもにとって、保育園・幼稚園への通園は「社会との最初の接点」であり、集団生活のはじまりです。
しかし現状では、体制や制度がまだ十分とは言えず、多くのご家庭が、園探しや受け入れの調整で最初の壁にぶつかります。
けれどこの時期だからこそ、「親として準備できること」や
「工夫できること」がたくさんあります。
それが、のちの就学にもつながる土台になることがあります。


よくある壁と困りごと
①受入れ可能な園が限られている
医療的ケアに対応できる園はまだ少なく、「どこにも通えないかもしれない」と不安になるご家庭も多いです。
▶参考リンク:
医療的ケア児サポート保育園(受入可能な園リスト掲載)(横浜市)
②看護職員・ケア対応人材の確保不足
園に意欲があっても、看護師などのスタッフを確保できず、受け入れが難しいというケースも。
③ケアと保育の分担・責任の境界が曖昧になる苦しさ
「親がケアを担うことが条件」とされることもあり、どこまでを誰が担うか、悩むことがあります。
④通園距離・交通の負担
受け入れ可能園が遠方にしかなく、通園時間や交通手段が大きな負担になるケースがあります。
⑤受入れ可否に関する不透明な判断基準
子どもの健康状態や集団生活への適応を理由に、断られることも。基準がはっきりしないため、納得しづらいことがあります。
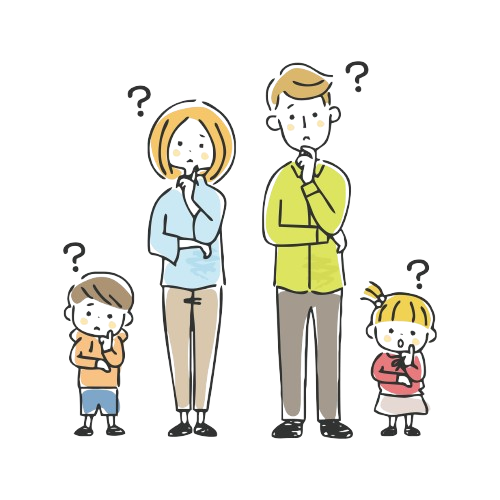
親としてできる準備と工夫
ケア内容を整理して“見える化”する
日々のケア手順や頻度、必要な配慮事項をマニュアルとしてまとめ、園に提示できるようにしておくと、受け入れ側も具体的に検討しやすくなります。
見学や体験保育で現場を知る
可能であれば見学や体験保育を申し込み、園の対応や雰囲気を自分の目で確かめておくと安心です。
早めの相談・情報収集
書類の準備を前倒しで
医療的ケア児を受け入れるためには、以下の書類が必要となる場合があります:
- 医師の意見書
- ケアマニュアル
- 利用申込書
- 指示書
これらの書類を事前に整備し、提出期限や見直しに対応できる体制を準備しておくことで、園との調整がスムーズに進みます。
また、自治体によっては医療的ケア児の受け入れに関するガイドラインや支援制度が整備されている場合があります。例えば、横浜市では「医療的ケア児保育受入ガイドライン」を策定し、必要な書類や手続きの流れを示しています。
他の自治体でも同様の取り組みが進められている可能性がありますので、お住まいの地域の福祉担当窓口や保育支援センターに相談し、最新の情報を確認することをおすすめします。
▶参考サイト:保育所等における医療的ケア児受入れ推進ガイドライン(横浜市)
地域の制度を知っておく
おわりに
保育園や幼稚園は、子どもにとっての「はじめての社会」。
その中で、安心して過ごし、楽しい時間を積み重ねていけることが一番大切です。
制度や受け入れ体制が整っていない中で動くのは、親にとって大きな負担ですが、
ひとつひとつの行動や準備が、「その子に合った通園の形」をひらいていきます。
焦らなくて大丈夫です。
あなたとあなたの子どもにとって、ちょうどいいペースと形を、一緒に探していきましょう。
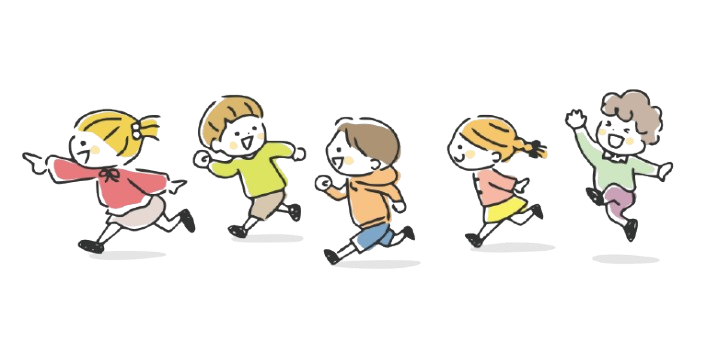
かんしん広場の関連ページの紹介
かんしん広場の「社会保障制度」のページでは、年齢別に受けられる支援制度についてご紹介しております。