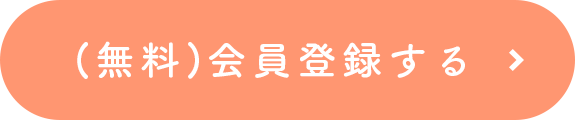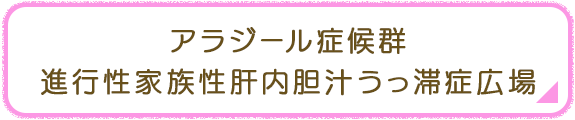別所 一彦 先生 インタビュー

滋慶医療科学大学
別所 一彦(べっしょ かずひこ) 先生
1997年大阪大学医学部医学科卒、1997年 大阪大学医学部附属病院研修医(小児科)、
1998年 国立大阪南病院研修医(小児科)、1999年 大阪大学大学院医学系研究科組織再生医学講座博士課程、
2005年 大阪大学大学院歯学研究科助教(口腔外科第一教室)、2009年 大阪大学大学院医学系研究科助教(小児科)、
2009年 Cincinnati Children’s Hospital Medical Center Department of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Staff Scientist、2013年 大阪大学大学院医学系研究科助教(小児科)、2013年 Cincinnati Children’s Hospital Medical Center Department of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Assistant Professor, Adjunct、2015年 大阪大学大学院医学系研究科講師(小児科)、2020年 大阪大学大学院医学系研究科准教授(小児科)、2021年 大阪大学医学部附属病院病院教授
2022年 大阪大学大学院医学系研究科招聘教授
2022年 滋慶医療科学大学大学院 教授 現職
「子どもと家族に、ずっと寄り添い続ける医師でありたい」
小児肝疾患・希少疾患と向き合う別所先生の信念と優しさに迫る
小児の医療は、病気だけでなく「生活」にも深く関わる分野です。
慢性疾患や難病を抱えた子どもたちにとって、医師は単なる治療者にとどまらず、時には心の支えであり、家族の一員のような存在になることもあります。
今回お話を伺った滋慶医療科学大学 別所 一彦 先生は、小児の肝疾患や希少疾患、さらには重症心身障害児の栄養管理など、複雑かつ専門性の高い分野を長年にわたり診療されてきた医師です。28年におよぶ臨床経験のなかで、どのような想いをもって子どもたちと向き合ってきたのか。その静かな語り口のなかに宿る、深い愛情と信念を伺いました。
Q:医師を志されたきっかけを教えてください。
A.「父が小児科の医師で、幼い頃から患者さんやご家族からの言葉が届く姿を見てきました。自然と、“医師という仕事は人の役に立つんだ”という感覚が、日常の中で育まれていたように思います。」
一方で、中学・高校時代には他の進路にも興味を抱いていたといいます。さまざまな分野への関心もありましたが、最終的に選んだのは医療の道でした。
「高校を卒業して進路を考えたとき、改めて“人のためになる仕事をしたい”という想いに立ち返りました。今振り返ると、やっぱり最初からこの道を心のどこかで選んでいたのかもしれませんね。」
Q:現在の専門分野に進まれた理由を教えてください。
A.「医師として臨床を続ける中で、病気そのものよりも、それによって“日常を奪われている”子どもたちの姿に心を動かされました。学校に通うことができない。学校に通えているけど、行事には参加できない。そんな状況を前にして、どれほど本人や家族が苦しんでいるか。そうした姿を見ているうちに、“この子たちの生活を少しでも良い方向に変える力になりたい”という気持ちが強くなっていきました。」
とりわけ印象に残っているのは、ご両親の葛藤です。病気の子を育てる中で、「自分たちが悪かったのではないか」と自責の念を抱く方や、「周囲に迷惑をかけてはいけない」と行事や集まりを遠慮される方も少なくありません。
「そうしたご家族の心の重荷にも、医師として関わっていけたらと思っています。」
現在は、小児の肝疾患、表皮水疱症、そして重症心身障害児の栄養管理を中心に、病気だけでなく、その先の暮らしまで視野に入れた医療を実践されています。......
☆本記事は、日本アラジール症候群の会のご紹介・ご協力のもとに作成しました。
※会員登録をいただくと、別所先生のインタビュー記事の続きを読むことができます。
プロフィール設定の”関心のあるもの”より「インタビュー」「医師」をご選択ください。
※アラジール症候群・進行性家族性肝内胆汁うっ滞症についての情報がご覧いただけます。
患者さんご家族の体験談や医師のインタビュー、患者会の紹介を掲載しています。