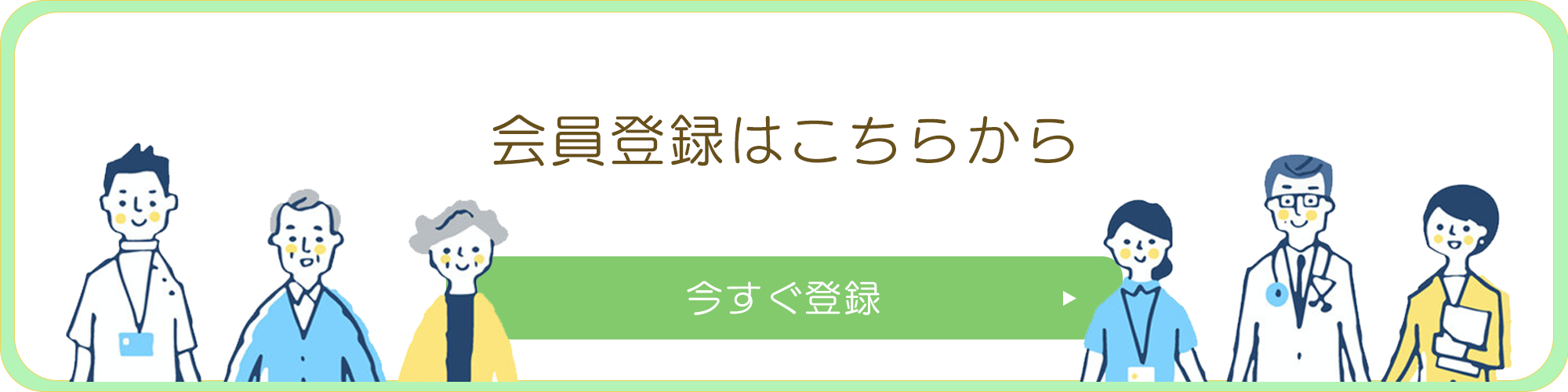「“学ぶ”って、わが子にとってどういうこと?
――難病とともに歩む子どもの就学を考える」①はじめに(シリーズ掲載)
2025/10/30公開
はじめに
「この子にも学校に通う日常を送らせてあげたい」
それは、子どもを育てる多くの家族が抱く、ごく自然な願いです。
病気や障害のある・なしにかかわらず、「友達と一緒に机を並べて学ぶこと」「行事に参加すること」「未来の選択肢を広げること」は、
子どもの成長を願うすべての親にとっての希望だと思います。
でも、日々の生活の中で“医療的ケア”が欠かせない子どもたちにとって、「通学する」「学校に通い続ける」というのは、あたりまえとは言い切れない、
たくさんのハードルがある現実です。
たとえば、日常的にたんの吸引や呼吸器の管理、胃ろうからの栄養摂取が必要な子どもにとっては、「学用品や制服をそろえればOK」とはいきません。
医師の意見書やケアの手順書の準備、学校との綿密な調整、吸引器や酸素ボンベの持ち込み、通学の交通手段――そうした一つひとつを丁寧に整えていくことが、「学校へ通う」という希望につながっていきます。
このコラムでは、幼稚園・保育園から、大学や専門学校まで。医療的ケアや難病を抱える子どもたち、そしてその家族が「進路を選ぶ」「学校に通う」ために直面する現実と、その中で育まれる工夫や希望について、シリーズ連載で、制度の情報や皆さんの不安の解決とともにお届けしていきます。
1. どのくらい付き添いが必要か、早めにイメージしておくと安心です
医療的ケアが必要なお子さんのうち、普通学校に通っている場合、12.7%の保護者が学校生活の中で付き添いをしているというデータがあります。
▶参考リンク:
令和5年度 学校における医療的ケアに関する実態調査結果(別紙2)(e-Govポータル)
もちろん、お子さんの状態や学校の体制によって、必要な付き添いの度合いはさまざまです。
だからこそ、入学前や転校の前に、次のようなことを少しずつ整理しておくと、あとがぐっと楽になります:
- 毎日のケア行為(たん吸引、呼吸管理、栄養管理など)が授業時間中に必要かどうか
- 看護師・認定特定行為従事者を学校が配置できるかどうか、時間帯や人員の体制
- 教員・看護師との契約・調整体制(非常時対応・休暇時代替など)
- 登下校時の付き添いが本当に要るか/交通手段の選択肢
こうしたことを早めに見通しておくと、「私が全部付き添わないといけないのかな?」という不安を、少しずつ整理できます。
学校と協力しながら、「できること」と「お願いできること」をうまく組み合わせていけるといいですね。
今すぐ全部を決める必要はありません。
でも、「どうしたら子どもが安心して学校に通えるか」を考えていくプロセス自体が、すでに大きな一歩です。
きっとその積み重ねが、お子さんにとっても、そしてお母さんご自身にとっても、心強い道しるべになっていくと思います。
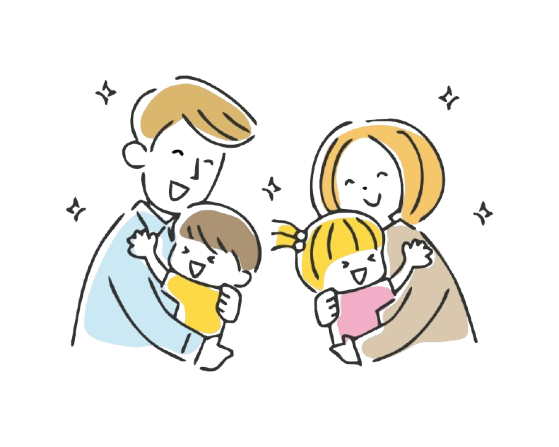
2. 付き添いを減らす・代わりを見つけるための工夫、少しずつ探してみましょう
学校での付き添いは、お子さんの安心や安全のためにとても大切なこと。
でも、それが長く続くと、お母さん自身の体力的・精神的な負担や、お仕事・家庭への影響も無視できなくなってきます。
実際、認定NPO法人フローレンスが主体で実施された、東京都在住の障害児・医療的ケア児のいるご家庭を対象とした調査では、付き添いを経験した保護者の約6割が「心身の負担を感じた」と答え、4割は「仕事に影響があった」としています。
▶参考リンク:
【都内在住の障害児・医療的ケア児家庭の学校付き添いを調査】約9割の保護者が学校付き添いを経験、心身の負担と仕事へも影響(2025年02月19日)(認定NPO法人フローレンス)
調査結果全文をダウンロードできます。
だからこそ、「全部ひとりでがんばりすぎなくてもいい方法」を、早めに探しておくことはとても大事です。
以下のような工夫が、そのヒントになるかもしれません:
- 協力してくれる人を増やす・備えておく
地域の支援者や、訪問看護師さん、介護職の方、学校の補助員さん、親族や友人など。
“いざというときに頼れる人”を少しずつ見つけて、付き添いの代わりになる体制を考えておけると安心です。
- 学校の時間割や教室の配置を工夫してもらう
教室の場所を保健室や看護師さんの近くにしてもらったり、先生や看護師さんのサポート体制を調整してもらったり。
「こんな風にできたら助かります」と、希望を伝えていくことも大切です。
- 遠隔モニタリングや通信支援の力を借りる
教室に見守り用のモニターをつけたり、看護師さんがリモートで様子を見てくれる仕組みを検討してもらうこともできます。
新しい技術が、付き添いをサポートしてくれる場面も増えています。
- 「慣らし期間」を作って、少しずつ手を離していく
最初の1〜2週間は、しっかり付き添って様子を見て、徐々に付き添い時間を減らしていくやり方もあります。
「いきなり全部任せる」のではなく、少しずつ慣れていくことで、子どももお母さんも安心できます。
付き添いの形に「正解」はありません。
でも、「私に合った形はどれだろう?」と考えながら、少しずつ工夫していけば、きっと“続けられるやり方”が見つかります。
がんばりすぎず、周りの手も借りながら、自分と子どものペースで整えていきましょう。
3. 「見える化」して共有することで、不安を減らし、つながりを強く
学校生活の中で不安を減らしていくために、とても大事なのが「情報の整理と共有」です。
お子さんのケアや対応について、関わる人みんなが同じ情報を持っていることが、安心と信頼につながります。
たとえば、次のような工夫が役に立ちます:
- 緊急時対応フロー(発作・体調急変時など)を、学校・看護師・保護者で事前に合意しておく
- 情報共有ツール(紙・デジタル問合せ票、連絡アプリなど)を使う
- 定期的な会議・振り返りを持つことで、ケア体制を調整していく
これにより、教員・看護師との意思疎通ミスを最小化できます。
4. 「働くこと」「暮らすこと」との両立を、あらかじめ見据えておく
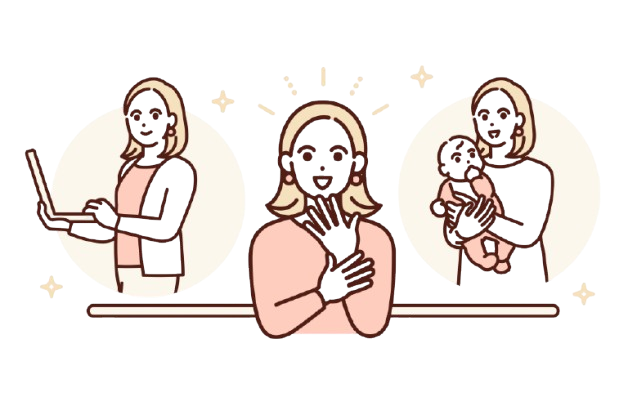
医療的ケアのあるお子さんを育てながら働くというのは、本当に大きなチャレンジです。
特に、お母さんが仕事の調整を引き受けるケースが多く、負担が集中しがちです。
「医療的ケア児の保護者における就労状況調査」でも、主に母親の働き方に制約が出ていることが指摘されています。
でも、だからこそ——
付き添いやケアが必要な時期を乗り越えていくために、「自分の働き方や暮らし方をどう支えていくか」を、早めに考えておくことがとても大切です。
以下のような視点が、きっと助けになると思います:
- 時短勤務やフレックスタイムなど、柔軟な働き方を職場と相談しておく
「朝は送迎がある」「午後はケアが必要」など、生活リズムに合わせた働き方ができるよう、前もって話し合っておくと安心です。
- 在宅勤務・リモートワークに対応できる仕事を確保する
職場との信頼関係を築きつつ、「どうしたら働き続けられるか」を一緒に模索していく姿勢も大切です。
- 休職や育児休暇制度を計画的に活用する
たとえば、入学前後のタイミングなど、特に手がかかる時期に合わせて休みを取れるよう準備しておくと、心に余裕が生まれます。
- 福祉制度・給付金・手当など、公的支援もしっかり活用する
支援制度を知っているかどうかで、生活のしやすさが大きく変わることも。必要な情報は、あとから詳しくご紹介します。
こうしたことを前もって少しずつ考えておくことで、「もし長く付き添いが必要になったら?」という不安にも、現実的に備えることができます。
お子さんのためにがんばることはもちろん大事。
でも、お母さん自身の生活や人生をあきらめないことも、同じくらい大切です。
無理のないやり方を探しながら、長く続けていける形を一緒に描いていきましょう。
▶参考リンク:
(論文)医療的ケア児の保護者における就労状況の調査(荒木 俊介 , 中村 加奈子, 柏原 やすみ, 江口 尚, 下野 昌幸)
5. 小さな安心を少しずつ積み重ねていく、“時間を味方にする”考え方
医療的ケアを必要とするお子さんの学校生活では、制度がまだ十分ではなかったり、学校側との調整がスムーズにいかないことも、実際によくあります。
でも、そんなときこそ大切にしたいのが、「いきなり全部を整えようとしない」という姿勢です。
“小さな安心”を、段階的に積み重ねていくこと。
それが、親にも子にも無理のない、現実的なアプローチになります。
たとえば、こんなステップが考えられます:
- 入学前に「慣らし期間」を設けてもらう
いきなり通学を始めるのではなく、まずは学校に「慣れる時間」を確保してもらうことで、お子さんも安心しやすくなります。
- 週1回の通学や“見学日”からスタートできないか、学校と話してみる
「今できること」を少しずつ増やしていくような通学スタイルも、ひとつの方法です。
- 最初は“ピロティ教室”や“仮教室”などで、教室や時間を限定する
音や人の多さが不安な子には、環境を整えることでスムーズなスタートが切れる場合もあります。
- 定期的な振り返りやモニタリングを、学校との“取り決め”として設けておく
学校とのコミュニケーションを「その場限り」にせず、計画的に見直していけると安心です。
- “お母さん自身”のケアも、ちゃんと作戦に入れておく
心理的サポート、休息の時間、話せる人・相談できる先。
「がんばる自分」にとっての抜け道も、戦略のひとつです。
完璧な制度も、完璧なスタートも、たぶん最初からはありません。
でも、「今できること」や「今ある支援」を上手に使って、小さな安心を積み上げていくことなら、今日からでも少しずつ始められます。
正解を目指すよりも、自分と子どもにとって「ちょうどいい形」を探していくこと。
時間を味方にしながら、焦らず、ゆっくりと進んでいきましょう
次回は、2025/11/06(木)に「幼稚園・保育園期:最初の壁と親の準備」についてお届けします。
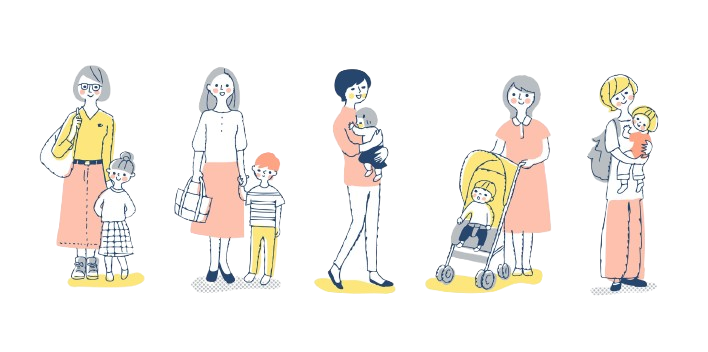
お役立ち情報の関連ページの紹介
お母さん自身のケアの一つとして、ひと休みできるサポート制度や方法のコラムを掲載しております。