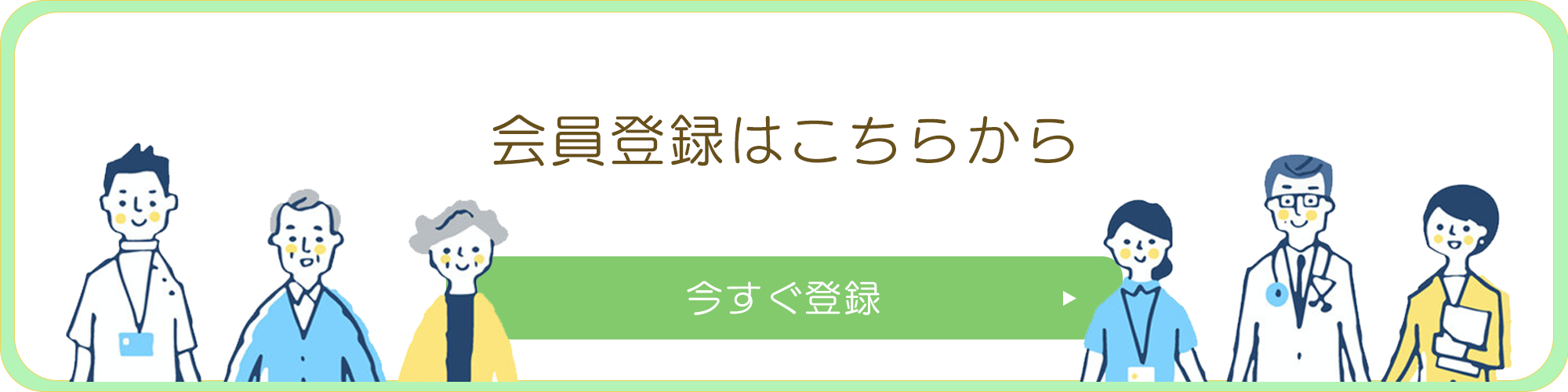医療的ケア児を支える社会保障制度|申請のコツと活用のヒント
医療的ケアを必要とする子どもを育てるご家族にとって、社会保障制度は非常に重要な支えとなります。
しかし、情報の収集や申請手続きには多くの課題があるのも事実です。
本記事では、Aさんの体験をもとに、社会保障制度を活用する際のポイントを整理しました。
病気の発覚と社会保障制度との出会い

「妊娠中に、子どもが先天性横隔膜ヘルニアであることが分かりました。
あまりにも突然のことで、ショックが大きすぎて、制度について調べる余裕がありませんでした。」と語るAさん。
胎児の治療と自身の早産予防の治療もしていく必要があり、医師から高額療養費制度の活用を勧められ、まずは何も考えずにすぐに手続きを進めたといいます。
出産後、社会保障制度を活用するまでの経緯
「生まれた後も、わが子の病状を受け止めることに精一杯で、社会保障制度のことまで考える余裕はありませんでした。」
そんな中、病院のソーシャルワーカーが医療費助成制度や訪問看護などの情報をまとめた資料を持ってきてくれました。
「制度を1から調べる時間も気力もなかったので、ソーシャルワーカーさんからの情報提供は本当に助かりました。」
Aさんが実際に利用した制度は以下のようなものでした。
※本文中のオレンジ色の文字は、タップすると関連情報ページへ移動します。
訪問看護では、看護師がサポートに入ることで、医療ケアの負担が軽減されただけでなく、「他愛もない話をすることで気持ちが楽になった」と精神的な支えにもなったそうです。
申請の流れとその課題
申請のプロセス
「入院中に、ソーシャルワーカーさんから『申請に必要な書類を読んでおいてください』と言われました。」
申請は以下の流れです。
1. 文書センターに様式を申し込む
2. センターが医師へ書類を依頼し、医師が記載する
3. センターへ書類が戻る
4. その後、家族へ書類が届き、自治体へ申請
センターから書類が届くまでには約2週間かかりますが、取りに行く手間があります。
また、郵送での対応も可能ですが、郵送費は自己負担になります。

自治体に申請後、審査会を経て承認されると手帳が発行されるが、発行には1~2か月ほどかかるといいます。
とはいえ、制度は遡って適用されるため、費用面での負担は軽減されました。
更新手続きの負担
「小児慢性特定疾患の更新手続きが大変でした。最初の申請と同じ手順をまた繰り返さなければならず、1つの制度ごとに1つの書類が必要なので、負担が大きいと感じました。」
また、役所や文書センターは平日のみ対応のため、働いている人はそのたびに休みを取らなければならないのが課題になっています。
「オンラインで受付できるシステムがあったら、とても助かると思います。」
自治体ごとの違い
「住んでいる地域と病院の都道府県が違う場合、医療費を一度全額支払い、領収書を持って自治体へ申請しなければならないのも負担でした。」
同じような状況にある方には、あらかじめ手続きの流れを確認しておくことをおすすめします。
社会保障制度を利用して感じたメリット
制度を利用することで、Aさんが感じたメリットを紹介します。
✔ 費用を気にせず受診できる
✔ レジャー施設などの割引制度がある
✔ 訪問看護で看護師のサポートが受けられる
「夜中でも困った時には訪問看護師さんが電話を受けてくれたり、病院との連携を取ってくれたりしたことで、助けられることが多かったです。」

社会保障制度を利用して感じた課題と改善点
制度を利用する中で、課題や今後の改善点も感じました。
Aさんが感じた課題や改善点を紹介します。
地域による認定の違い
「同じ疾患でも、地域によって申請が通りやすい所とそうでないところがあると感じています。」
「全国で統一された基準があれば、もっと公平に利用できるのではないかと感じています。」
その違いに戸惑い、制度の利用を諦めてしまう人もいるかもしれません。
障害者手帳のデジタル化
「障害者手帳がアプリでも使えるようになったそうですが、まだ認知度が低いと聞いています。世の中にアプリの認知度がもっと広まえれば、より便利になると思います。」
アプリと手帳本体の良い点をうまく利用することでより便利になると考えています。
親の負担軽減
「子どもへの制度は充実しつつありますが、親や家族への支援はまだ少ないと感じています。」
幼稚園・保育園の卒園から小学校入学までの間の相談窓口がないため、ご家族での不安が続きます。
「例えば、発達がゆっくりな子は親も入学までにいろいろ不安があるのですが、そのようなモヤモヤを聞いてアドバイスしてもらえるところがないと感じています。『小学校に入ってから相談』というケースが多く、それまでの期間をサポートしてもらえる窓口があったらいいなと思いました。」
同じような不安を抱えている方は、早い段階から支援先や相談先を探しておくと、少し気持ちが楽になるかもしれません。
これから制度を利用する方へのアドバイス

・どこに何の情報があるかを把握しておくことが重要(厚労省、こども家庭庁、自治体、難病情報センター、病院などのホームぺージ)
・患者会で病気の詳しい情報を聞く
・制度について知るために積極的に情報を取りに行く(新聞、インターネットなど))
・一人で抱え込まず、相談できる場を活用する(例:患者会での交流)
社会保障制度をスムーズに活用するためには、事前の準備が重要です。
どのような情報が必要なのか、どのような制度が利用できるのかを事前に収集しておきましょう。
まとめ:社会保障制度を味方に、安心した子育て
医療的ケアが必要なお子さまを育てるAさんが実際に利用した支援制度をまとめました。
Aさんと同じように、お子さまのケアに日々向き合っているご家族の皆さまにも、きっと役立つ情報があるはずです。
それぞれの制度の概要や相談窓口をご確認いただき、ぜひご自身の状況に合わせて活用できるものがないか、お考えの際に参考としていただければ幸いです。
| 制度 | 概要 | 相談窓口 |
|---|---|---|
| 小児慢性特定疾病医療費助成制度 | 厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている児童等の医療費の一部を公費で助成する制度。 | お住まいの都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市の窓口、保健所、各自治体の福祉部障害者福祉課など |
| 育成医療 | 身体の障がいを除去・軽減するための手術など、確実な治療効果が期待できる18歳未満のお子さまに対し、必要な医療の給付を行う制度 | お住まいの市区町村の障害福祉課、健康サービス課、医療的ケア児支援センター、医療的ケア児等コーディネーター |
| 乳幼児医療費助成制度 (子どもの医療費助成) | 乳幼児の医療費の自己負担分を助成する制度。 自治体によって対象年齢や助成範囲が異なります。 | お住まいの市区町村の子育て支援課、児童手当係、保健センターなど |
| 訪問看護 | 主治医が必要と認めた場合に、看護師等が自宅を訪問し、医療的ケアや療養上の世話を提供するサービス。 | かかりつけ医(主治医)、訪問看護ステーション、お住まいの市区町村の障害福祉課、こども福祉課、医療的ケア児支援センターなど |
※各制度名には、その制度についてさらに詳しく解説している当ウェブサイトの記事ページへのリンクが設定されています。
より詳細な情報や申請手続きの具体的な流れを確認する際にご活用ください。
最後に
Aさんの体験から、社会保障制度の活用は子どもの医療的ケアを支える重要な柱となることが分かりました。
しかし、申請の複雑さや地域による認定基準の違い、親への支援の不足など、改善すべき課題も多く存在しています。
「子どもに対する支援は充実してきていますが、看護をする親の負担が軽減される仕組みがもっと整ってほしい」とAさんは語ります。
今後、オンライン申請の導入や制度の全国統一化が進むことで、より多くのご家族が公平かつスムーズに支援を受けられるようになることが期待されます。
同じような状況にいる人は、一人で悩まず、患者会や専門家とつながることで、必要な情報を得ることができます。
制度の活用には積極的な情報収集が鍵となるため、「どこで何を調べればいいのか」を知っておくことが大切です。
社会保障制度は、患者や家族にとって心強い支えとなる一方で、改善の余地もあります。
今後もこうした声を積み重ねることで、より多くの人が負担なく必要な支援を受けられる社会へと近づいていくことでしょう。
Aさんの経験が、制度利用を考えている人にとって少しでも役立つことを願っています。