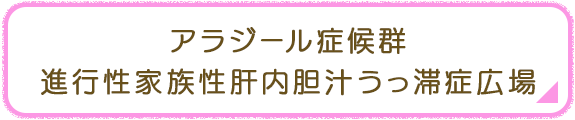中野 聡 先生 インタビュー
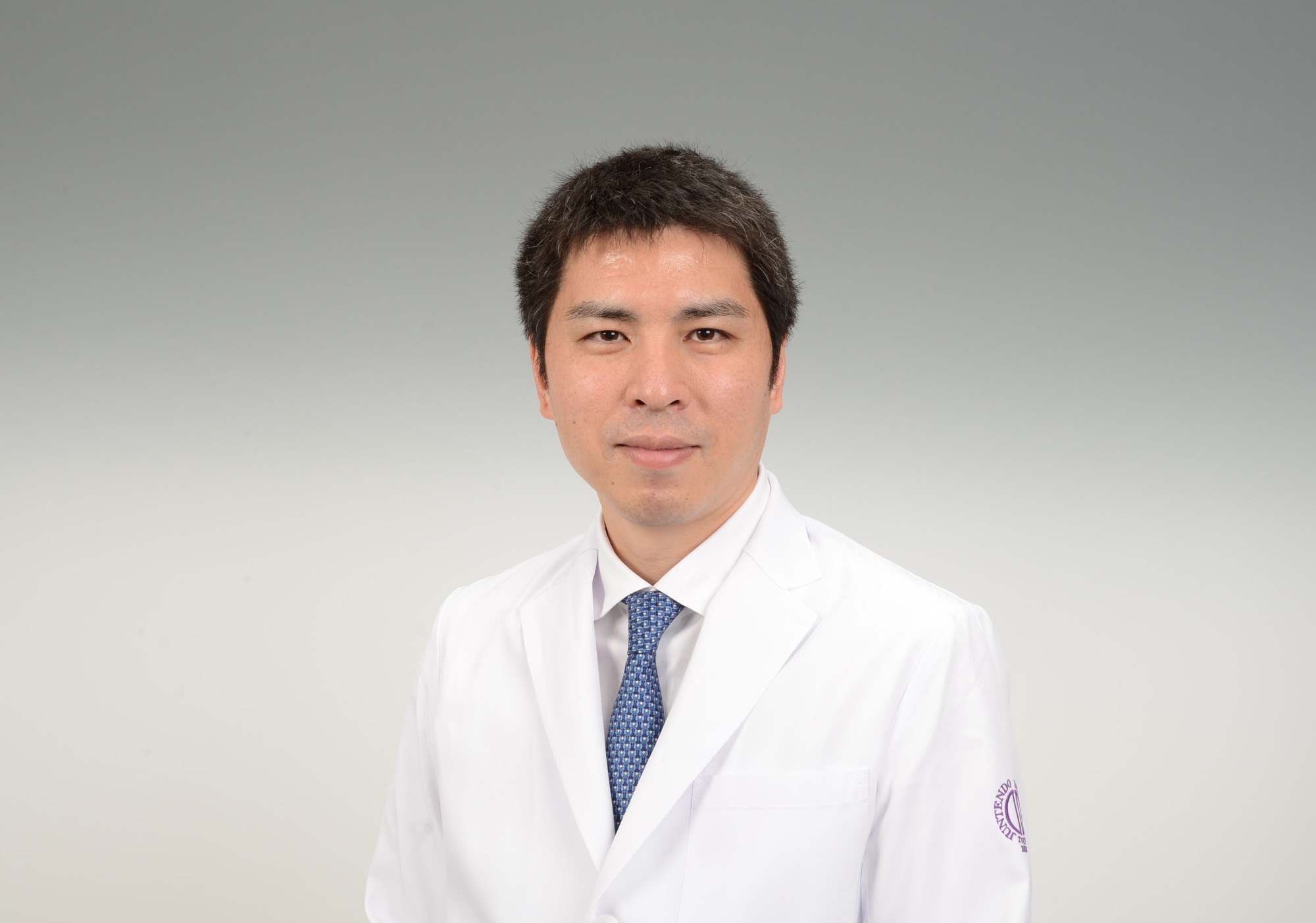
順天堂医院
中野 聡(なかの さとし) 先生
順天堂大学(医学部卒2010年)
「医師としての本質とは何か」
テクノロジー時代における“寄り添う医療”の意味を問う
患者の声を聞く——。 それは、医療の世界で長らく言われ続けてきた言葉である。
しかし現場では、時間的・制度的な制約の中で、その声が十分に汲み取られているとは限らない。
今回お話を伺ったのは、順天堂医院/中野聡先生。小児科医として臨床と研究に取り組む現役医師。現代医療の中で忘れられがちな“本質”について語っていただいた。
医師になったきっかけ
「実は、最初から医師になりたかったわけではないんです。」
そう穏やかに語りながら、彼は学生時代のことを振り返る。
彼の家族や親せきには、医師・看護師・薬剤師といった医療関係者が多い。
周囲からは「当然、医者を目指すのだろう」と思われていたが、本人の心は少し違っていた。
「“敷かれたレールの上をそのまま歩く人”と思われるのが嫌でした。だからこそ、高校生のときに、世の中にはどんな仕事があるのかを改めて調べたんです。」
そうして見えてきたのは、「仕事」というものの多様さ、そして「自分は何のために働くのか」という問いだった。
「会社員として働く姿を想像したこともあります。頑張れば業績を上げられるだろう、という根拠のない自信もありました。でも、それで誰かが不幸になることもあるんじゃないか、とふと思ったんです。そう考えると、自分の頑張りが本当に意味のあるものなのか、分からなくなりました。」
迷いの中で出てきた答えは、「人の役に立つ仕事をしたい」という素朴でまっすぐな気持ちだった。
「不幸になる人がいない仕事がしたい。そう思ったとき、医師という仕事は悪くないなと思ったんです。」
その思いを担任の先生に打ち明けると、先生は高校生を対象にした医療体験のチラシを手渡してくれた。
実際に病院を見学し、医療現場の空気に触れたことで、心の中で何かがはっきりと形になった。
「その風景を見て、医師になろうと決めました。親の影響というより、自分の意志で決めたかったんです。」
その後、医師として歩み始めた彼は、研修医時代に「臓器単位ではなく、人間全体を診る」医療に惹かれていった。
「医療って、どうしても“どこの臓器が悪いか”というふうに分けて考えがちです。でも、私は患者さんの“人格全体”を診たいと思った。そう考えたときに、小児科が自分に合っていると感じました。」
子どもを診るということは、病気だけでなく、その子の生活や家族、成長のすべてに関わることでもある。
だからこそ、「全力で医療をすることが肯定される場所」だと感じたという。
「自分がやらなくても他の誰かがやることなら、それでもいい。でも、誰もやりたがらないこと、やる人が少ないことを自分が引き受ける――。それこそに意味があると思っています。」
彼の原点には、そんな静かな情熱が息づいている。
医師の役割は「治す」だけではない
「今の医療では、薬を使って治すことが医師の役割とされがちです。でも、それが本当に医師の本質なのでしょうか?」
穏やかな口調でそう問いかけるのは、日々の診療に加えて、患者や家族との“対話の場づくり”にも積極的に取り組む医師だ。
彼は、現代医療が「病気を治す」という一点に過度に重きを置きすぎていることに、かねてから違和感を抱いてきたという。
「医師という職業は、2000年以上も前から存在していました。当時は、今のように薬も検査機器もありません。それでも人々は医師を必要としていた。なぜかと考えると、医師の原点は“治す”ことだけではなく、“話を聞き、苦しみに寄り添う”ことにあるのだと思うんです。」
彼が勤務する診療科には、完治が難しい病気と向き合う患者が多い。
だからこそ、「治せない」状況の中で、どんなふうに患者と関わるかが問われる。
「もちろん、医学的に最善を尽くすことは大前提です。でも、それだけでは足りない場面がある。つらさや不安を言葉にできるよう支え、心の拠りどころになることも、医師にしかできない大切な役割です。」
そう語る彼の表情は穏やかで、確かな覚悟を感じさせた。
“治す”ことだけが医療ではない。病気とともに生きる人の人生に寄り添うこと――。
その姿勢こそが、医師という存在の根源にあるのかもしれない。.....
☆本記事は、日本アラジール症候群の会のご紹介・ご協力のもとに作成しました。
※会員登録をいただくと、中野先生のインタビュー記事の続きを読むことができます。
プロフィール設定の”関心のあるもの”より「インタビュー」「医師」をご選択ください。
※アラジール症候群・進行性家族性肝内胆汁うっ滞症についての情報がご覧いただけます。
患者さんご家族の体験談や医師のインタビュー、患者会の紹介を掲載しています。